
4日に行われた総裁選を制し、新たな自民党の顔となった高市早苗氏。彼女が新総裁の座を射止めることに成功した背景には、欠かせない勢力が存在していたようです。今回のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』では作家で米国在住の冷泉彰彦さんが、日本の政界に大きな影響力を持つ「地方名望家」とはどのような人々なのか、そして彼らの行動原理とは何かを解説。その上で、高市総裁が地方名望家を「墓場に連れてゆくべき理由」を考察しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/メルマガ原題:高市早苗氏と地方名望家の「関係」を考える
日本政界に及ぼす大きすぎる影響。「地方名望家」と高市早苗の関係
高市早苗氏が自民党の総裁に当選しました。当選に至った経緯としては、ライバルの小泉進次郎陣営に「優勢」であったゆえのスキがあったとか、高市陣営の本気度が上回ったなどという解説がありますが、話半分は本当で、半分は風評という程度に理解しておけば良いのではと思います。
テクニカルには、連立工作に関して、維新に接近していた小泉氏よりは、高市氏の方が柔軟に動けそうという思惑が議員たちにはあったのだと思います。総裁選の有権者、つまり自民党の国会議員の行動原理は「次の選挙で落ちない」「今の任期を全うしたい」ということであって、これが何としても至上命題だからです。ですから、連立を安定させて多数与党になれば解散総選挙は先へ伸びるし、与党が安定すれば次の選挙で「自分が当選」する可能性は高まるわけです。
その意味で、公明党は表面的にはハト派で、高市氏と距離を置いているようにも見えますが、長年の自公連立の中で、閣僚としてやってきた高市氏は、公明とのチャネルもある、そんな安心感もあったのだと思います。高市氏といえば、選挙区の関係で教派神道の大手である天理との関係が濃く、創価=公明とは全国的に競合関係があるという事情もあるかもしれません。
ですが、公明というのは、ある時点からは都市周辺の比較的豊かな自営業や専業主婦の経済的基盤が高齢化。そこからは高齢者の権益保護のために、政権に密着する方向に転換せざるを得なかったので、余程のことがない限りは保守政権に同伴してゆくでしょう。現在進んでいる「高市氏への拒否反応」というのは、型通りの儀式のようなもので、結果的には連立を維持するのではと見ています。
その上で国民民主との間で、何らかの政策合意を取り付けて当面の政治運営をするというのがシナリオのようです。後は、終盤に来て麻生太郎氏との手打ちがあったようですが、その席で高市氏は極端な積極財政は引っ込める密約をしたのかもしれません。これは非常に大きな点で、仮に麻生氏が相当な「釘刺し」をしたのだとすれば、財政規律をぶっ壊すところまでは暴走しないということで、当面は見ていって良いのだと思います。
ちなみに、今回の株高、円安はいわゆる「サナエノミクス」というのが、基本的に金融緩和政策という期待の現れのように見えます。ですが、これも成立可能なゾーンというのは、極めて狭い角度になっているので、暴走もなければ即時失速もない程度で推移すると見ていいと思います。
円安と株高ということでは、実は現在の日本の大型(時価総額の大きな)株というのは、価格形成は国外の投資家による部分が大きいわけです。その場合は、円建てで株が上がっても、同時に円が下がればドル建て株価はイーブンなので、話としては別に驚くようなことが起きているわけではありません。
「地方名望家」とは一体いかなる人々を指すのか
そんなわけで、高市政権の方向性は実質的な部分では、安倍=菅=岸田=石破の路線と大きくは変化しないと思われます。と言いますか、よくも悪くも官僚組織の上げてくる、そして当面は実施可能であるゾーン内の政策が繰り出されて来るのだと思います。財務省が警戒しているなどという噂は、あくまで噂に過ぎないと思います。
そうは言っても、総理が交代し、少なくとも多少はリベラル色のあった石破政権から、かなり右派色を出していた高市政権へという変化は、国の持っているイデオロギー的な気分を変えるということはあると思います。
その場合に鍵となるのが「地方名望家」との関係です。この「地方名望家」というキーワードは、高市氏という政治家の足跡も、また権力の源泉にも深く関わってくるものであり、これからも注意して見ていく必要があるからです。
比較的有名なエピソードですが、高市氏は松下政経塾からワシントンDCに送られて、当時の民主党下院議員の事務所で事実上のインターンをしていたわけです(肩書については諸説ありますが、まとまった期間、確かに仕事をしていたのは間違いないようです)。帰国後は、若手の女性コメンテーターとして、例えば田原さんの「朝生」などで注目されていました。
その頃か、あるいは議員になってすぐだったか、いずれにしてもアメリカ体験を売り物にしていた時期の高市氏は、「日本では選挙に落選すると候補が支持者に対して土下座するが、自分は絶対にしたくない」というようなことを言っていたのを覚えています。当時の自分としても、これはかなり共感できる内容でした。
ですが、その後、二大政党制が部分的に動く中で、高市氏は実際に落選を経験します。そして、落選にあたっては、前言を翻して実際に支持者に対して土下座をしたようです。このエピソードは、彼女の中で何かが壊れ、何かに屈服した事件、そのような印象で見ていました。また、人間はそのような経験を通じて「ダークサイド」に行くことがあるのだ、そんな印象も持ったのを覚えています。
それはそれで一種の説明にはなるのだと思います。ですが、今は少し違う見方をしています。それは、高市氏というのは日本の近代に大きな存在を占める「地方名望家」の権力、これに屈しつつも、あるいは利用してきた、一種の霊媒師と言いますか、巫女のような存在、そのように見ることも可能だということです。
この「地方名望家」というのは、大正時代の二大政党制において、政友会の支持母体として日本の歴史に登場したグループです。それは、土地の大規模所有制を基盤としつつ、地方に政治経済面での大きな基盤を持った家父長制の組織を言います。その多くは、戦前においては納税額によって議員になったり、あるいは当時から現在でもそうですが、地方議会を支配したり首長になっていたりします。
家業としては製造業であったり、運輸、サービスなどを独占的に経営し、スケールは小さいながらその地方における政財界の要となっている存在です。彼らの原点は恐らく、第一次大戦の戦時景気であり、同時にその直後の震災と戦後の過剰在庫がもたらした不況であったと思います。こうした浮き沈みの経験を通じて、彼ら「地方名望家」というのには、4つの行動原理が生まれました。
明日を生き延びるためには手段を選ばない地方名望家
1つは、中長期視点などというのは幻想であり、あるいは富裕な都市インテリの特権的な視点であり、自分たちは「明日をもしれない存在」だという、徹底した短期的視点ということです。明日を生き延びるためには手段を選ばない、何故なら明日を生き延びなければ明後日はないという生存本能とでも言って良いものです。
2つ目は、まずは東京への、そしてその先にある米英への屈折した対抗心です。米英が主導する世界秩序、そして金融秩序、その出店としての東京というのは、自分たちが生き延びるための生存闘争には、根本的な対立があるという認識。そして何よりも、米英の描く理想主義などに、自分たち異民族を見下げる視線を感じて、これを東京の地方への蔑視に対する反発を重ね、これに対する発奮と言いますか、対抗心を深く秘めるという体質があります。
3つ目は、政界との癒着です。経済は経済として回すべきで、とにかく企業を大きくして市場から資金を調達して世界に雄飛するという発想は、この地方名望家には弱いのです。そうではなくて、まずは地方政治、そして中央政界に癒着して、官需を引っ張って、自分たちの生存の基盤にする、それが確実であり安心だという行動原理があります。そこには公私混同や癒着、汚職があるという反省は、発想法として薄いのです。
4つ目は、自分たちに敵対するイデオロギーへの根源的な憎悪です。まず、自分たちが回している中小規模の企業活動を危うくする組合や、その背後にある左翼イデオロギーに対しての徹底的な憎悪がデフォルトとしてあります。女性の権利や、平等思想なども同様に敵視します。どうしてかというと、自分たちの企業内の行動原理が、近代ではなく前近代の封建的なイデオロギーであるために、これに対する挑戦者は徹底して憎むということになるからです。
この4つの行動原理を持った「地方名望家」こそ、若き日の高市氏に土下座をしいて屈服させ、同時に今まさに、その高市氏を総裁へと押し上げたのでした。
この地方名望家の影響力を政治エネルギーに転じるという役割は、戦前の政友会から戦後は清和会福田派へと引き継がれ、現在に至っています。そして、現在でも政界に大きな影響力を行使しています。その一方で、その行動原理はそのほとんどが賞味期限切れとなっており、今こそ「大正以来の地方名望家」の影響力を削ぐことでしか、日本は先へ進めないとも言えます。何が問題なのか、3点ほど申し上げたいと思います。
「外国人排斥」というムードと地方名望家の関係
1つは、その集票マシンです。地方名望家なる存在があり、その存在が日本の保守政治を支えているとして、彼らは保守党に従順というわけでもありません。例えばですが、細川政権、鳩山政権などの政権交代があった際には、地方における左のバラマキに反応して票が動きました。
また、地方保守票と言っても中選挙区時代の名残りで、一枚岩ではないのです。例えば清和会系が弱く、宏池会系が強いとか、各派が争っているなどの県もあります。これに対して、中央政界としては、以前はバラマキで対応していたわけです。公共工事を大きな「餌」として集票を行っていたのです。ですが、現在は財源難から政治的なバラマキは難しい時代です。
更に、人口減が直撃する中では意味のある、つまりリターンのある公共投資は限られてきます。そんな中で、自陣営に有利になるように、地方票をまとめるには、どうしても饗応が必要になってきます。と言いますか、昔から饗応はやってきたわけで、最低限これは今でも止められないというわけです。ところが、岸田政権の裏金摘発のドラマの結果、こうした饗応に使う資金も源流が絶たれてしまいました。
もう観劇バス旅行も、桜を見る会も資金的にできない時代、またネットなどの監視の厳しい中では、非常に難しくなっています。そんな中で、依然として地方名望家がまとめてくる地方票を確保するには、イデオロギーしかなくなっている、そんな中で、高市というブランドはある種の力を持ったのだと思われます。
2つ目は、では昨今急速に話題になっている「外国人排斥」というムードと地方名望家の関係ですが、これは、実は非常に複雑です。一見すると、地方名望家はイデオロギー的な保守であり、それこそ「外国人排斥」を先頭に立って主張しそうに見えます。ですが、現実は違うのです。
多くの地方の中小企業のうち、製造業に関しては、勿論低付加価値のもので地場産業として残っているものもあります。ですが、中付加価値のものは、年商100億前後の商売でも、90年代以来どんどん国外に製造拠点を出しているのです。つまり、地方名望家と言っても最低限の国際化はしています。
一方で、内需対応の産業ですと、観光旅行業などの人での必要な部分は、それこそ現在はその多くを外国人労働力に依存しています。また観光旅行業の場合は、内需のようで実態は訪日外国人、つまり事実上の外需依存だったりします。製造業も、農業もそして建設も、外国人労働力がなければ回りません。
だからこそ、安倍政権は猛烈な勢いで外国人労働者を入れたわけです。地方名望家というのは、実は暗黙の存在として、この動きに期待しており、安倍政権は見事にこれに応えたということが指摘できます。
国際問題ということでは、日中関係もそう簡単ではありません。地方名望家で、清和会系というグループは、一見すると中国に対して厳しそうですが、実情としては違います。実際は、工場を中国に持っていたり、部品や素材産業の場合は中国企業が大口の納入先だったりします。それこそ観光旅行業においては、今でも中国人旅行者の需要は業績に直結します。
古い話ですが、改革派を標榜して都市の票を掘り起こした小泉純一郎政権が、アッケラカンと総理の靖国参拝を行って、事実上は中国との首脳外交を拒んでいたわけです。その際には、日中関係は「政冷経熱」だなどと言われていました。これに対して、直後に登場した第一次の安倍晋三政権は、日中の首脳外交を再開しましたが、これも中道シフトと言うよりも、支持基盤であった地方名望家の利害を代表しての行動であったと考えられます。
「一方的な保守」とは違う地方名望家の複雑な心理
3つ目は、イデオロギーです。地方名望家は保守でありますが、その中身を見ていくと、国外の市場が大事、中国が大事、また外国人労働力も、訪日外国人も極めて重視します。ですから、行動原理としては反鎖国であり、国際化推進であるわけです。そうなのですが、先程申し上げたように、地方名望家の中には、頑固な保守思想があるのは事実です。
そうした保守イデオロギーの受け皿としてあるのが、例えば夫婦別姓反対であったり、LGBTQ擁護への反対であったりするわけです。この辺は実は都道府県でかなり濃淡のある話であり、例えば稲田朋美氏の立ち位置が中道になってきているのは、選挙区の福井が「ジジババの子育てに支えられた共稼ぎ社会」になっていることの反映だったりします。
もっといえば、自民党などの保守政党は「拉致被害者救出」のメッセージだとして、青いリボンのバッチを「いつでも」着用しています。この拉致問題については、例えば「北の当局に忠誠を誓う代わりに日本の親族とのコミュニケーションを許されている」人などもいるわけですが、青バッチの人たちは、そうした人たちを、悪しき政権に妥協した裏切り者として憎んだりはしないわけです。
つまり、アンチ金王朝という強い政治的メッセージと言うよりも、「家を出て戻ってこない息子や娘」への親の思い、といった部分で琴線に触れているのだということが言えます。拉致被害者への思いの裏には、多くの「地方名望家」が都会に出ていって帰ってこない息子や娘を「可能なら奪還したい」と思っている微妙な深層心理があると見ていいと思います。
何を申し上げたいのかというと、この地方名望家の心理というのは非常に複雑であり、一方的な保守というのとは違うのです。その独特の心理に寄り添うことが、この高市早苗という人にはできているということなのだと思います。そして、あえて申し上げますが、高市政権ができるということは、イコール、こうした地方名望家の伝統を最後の最後に終わらせて、彼らを墓場に連れて行くことになる、希望的観測を含めて、そんな見方をしています。
それでは、最後に、仮に連立工作が順調で、15日に高市新政権が発足した場合に、その政権はどんな方向性を示すのかを占っておこうと思います。
まず、財政規律については、選挙戦までの期間では相当に緩めて国内投資をするような姿勢がありました。ですが、最終的に麻生氏との提携が成立した中では、一定の枠が設定されたと見ています。
勿論、税調の宮沢氏に「お引き取り」いただくなど、多少の調整はあるし、何よりも国民民主との「手取り」問題の調整もしているようです。また、何か具体的な物価対策をしないと、現状は乗りきれず、総選挙など夢のまた夢というのは事実です。そうではあるのですが、無謀な領域に突っ込むことは回避されるのではないかと見ています。
次に為替については、物価を考えると円高に戻したいところですが、円安政策で行くしかなく、実際にこの点では行き過ぎにならない範囲で金融緩和気味に進むこということになりそうです。既に市場はその方向で反応しています。
今まさに次期内閣総理大臣に求められるもの
日米関係については、平均的な自民党政治家よりは米国の現状についての情報はあり、また判断の勘もあると期待しています。そのうえで、石破政権が赤沢氏を何度も派遣してやってきたことは、100%尊重して動くし、それ以外の選択はないであろうと思っています。27日にトランプ氏が来日した際が、恐らくは外交デビューとなると思いますが、大失敗はしないでしょう。
日中関係についても、前述した通り、地方名望家の支持を基盤とする中では、極端に悪化させる動機はありません。小泉政権から第一次安倍政権に移行した際のように、自然な日中外交を志向するだろうし、それでいいと思います。多少は言動の中で「保守イコール、アンチ中国」的な姿勢も見せるかもしれず、またそうでないと保守票の逃げるのが怖いということはあるでしょう。ですが、そうしたタカ派的言動も一定の枠内で止めると見ています。
一つ大きな懸念があるのは、仮に高市政権が現実主義に進むとして、その場合に、地方名望家は抱き込んでも「都市の現状不満票」が依然として逃げていくという可能性です。その上で、仮に総選挙があったとして、参政党やれいわ新選組などの両翼が更に票を伸ばす、そして政局が依然として不安定になるという可能性です。
これを避ける意味合いもあって、国民民主と提携して「手取り」改善策を実現することは、高市氏にとって重要な問題になりそうです。では、麻生太郎的な視点での「中長期の財政規律」から見た「国家破綻にならない範囲」というのが、玉木雄一郎的な視点から見た「国民の怒りが収まるレベル」に重なるのかどうかということです。
全く重ならないのであれば、政権存続は難しくなります。高市政権の運命は、石破、岸田のパターンと全く同じになるでしょう。そうではなくて、とにかく、中長期的な視点からは何とか耐えられる、それでいて国民の不満は何とか抑えることができるような政治、こちらが高市氏には求められます。
仮に数字が重なるゾーンがない、つまり国民へ向けた物価対策と、中長期の国家存続に必要な財政規律の間に「連立方程式の答えがない」ということも、あり得ます。その場合に、それでも落とし所を見つけて、その方向に全体を牽引する、その推進力と合意形成力というものが、今まさに次期内閣総理大臣には求められるのだと思います。
image by: X(@自民党広報)
MAG2 NEWS

 1 週間前
3
1 週間前
3



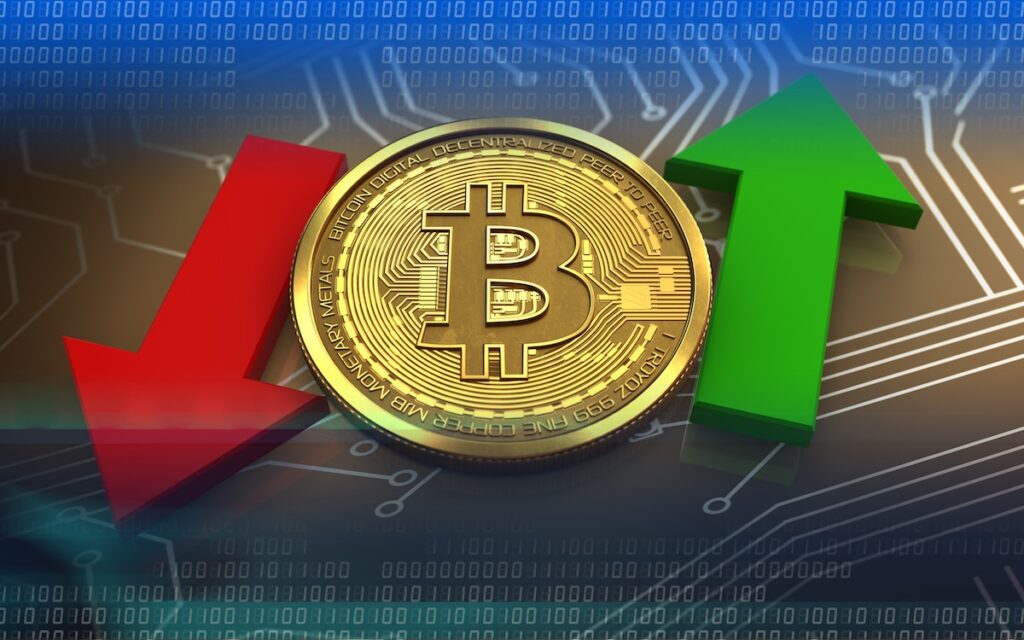

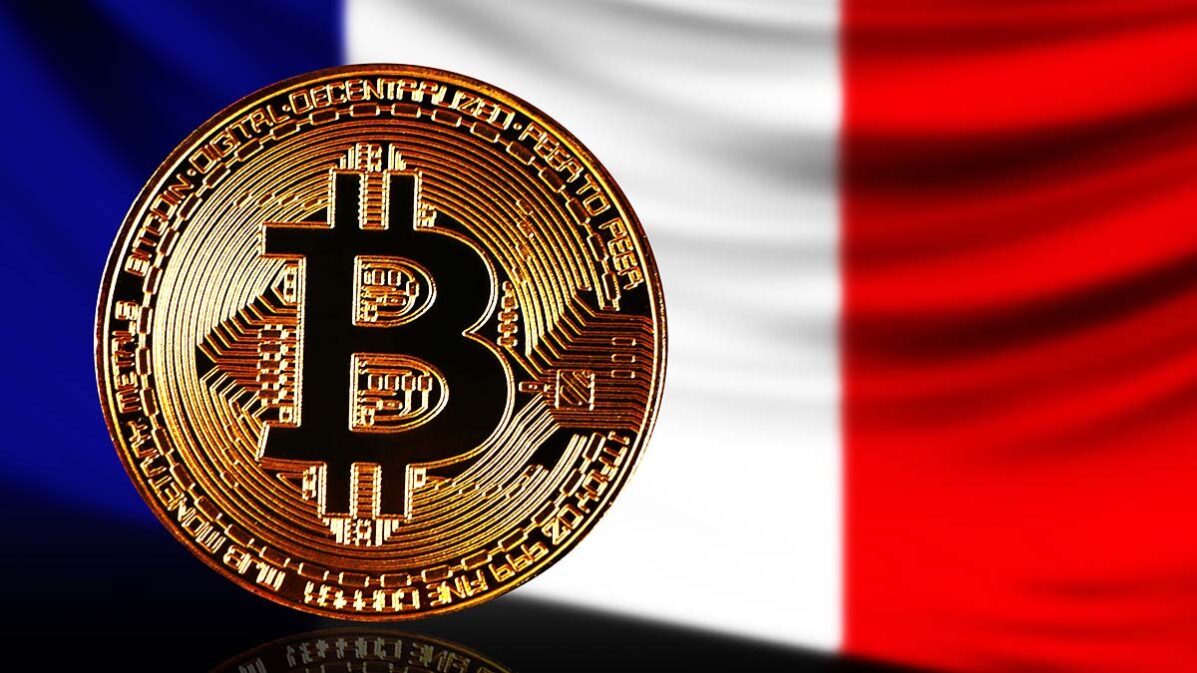


 English (US) ·
English (US) ·  Japanese (JP) ·
Japanese (JP) ·