
石破氏の退陣に伴う臨時総裁選を、いわゆる「フルスペック型」で実施することを決めた自民党。危機的状況を迎えていると言っても過言ではない自民党ですが、その舵取りを担う総裁にはどのような資質が求められているのでしょうか。今回のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』では作家で米国在住の冷泉彰彦さんが、3つの要素を挙げ各々について詳しく解説。その上で、どの人物がこうした「高いハードル」を超えられるのかを見極めることが重要だと指摘しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:日本の政局を判断する三重の視点
総裁選に打って出る候補者は理解しているか。日本の政局を判断する三重の視点
結局、石破氏は辞任を表明しました。一般のメディアでは多くは語られていないようですが、テクニカルには「臨時の両院議員総会の開催が不可避」「その場合は総裁解任が不可避」「解散権行使を真剣に検討」という事態に至ったようです。
この話には続きがあり、「解散には詔書への閣僚の署名が必要」「だが、多くの閣僚は署名を拒否」「閣僚を罷免し、自分が全閣僚を兼任しての解散も検討」「だが、その場合はイメージが極端に悪化」というシミュレーションの結果、ゲームオーバーになったとされています。
問題は石破氏が「個人的にそこまで嫌われていた」というような「セコい」話ではないということです。自民党内には、「石破だから解散したら大負けする、となると自分の議席も吹っ飛ぶのでイヤ」という感触があるのかもしれません。ですが、これは違うと思います。また野党の中には「今の石破と連立を組んだら次の選挙で負ける」という思いもあるでしょう。これも違います。
問題は、今の日本の政局には一種の三重構造のメカニズムがあり、そのゲームのルールを良く理解しないと、一発でゲームオーバになるということです。
まず、1番目はレイヤーの表層です。直近の課題がゴロゴロあり、世論の関心もあるし、仮に解散総選挙となれば争点になる可能性が高いわけです。ですが、そのどの課題も正解は簡単ではありません。前世紀のように「保守=現実」「革新=ファンタジー」的な二分法は消滅しましたし、2010年代のように「体制=バラマキ+既得権益」「アンチ=小さな政府、納税者の反乱」という二分法も成立しなくなっているからです。
代表的な例がコメと物価です。まずコメに関しては、それこそ「令和のコメ騒動」ということでコメの異常な高値が続いています。2025年の新米が出始める中で、備蓄米も平行販売されており、新米の場合は5キロで5,000円近い値段も出ているようです。一方で、例えば、現在のアメリカにおける日系スーパーなどでは、日本産の短粒米が5キロ(11ポンド)で20ドル(2,900円)前後ですから、価格が逆転しているぐらいです。
アメリカのスーパーでは、この「コメ騒動」が話題になって以降も、断続的に「JA(全農)フェア」などと銘打って、ブランド米の特売キャンペーンがされています。つまり、JAはハッキリと輸出促進をしているわけです。一方で、日本国内では、長年の減反政策、高齢化による離農などが複合して品不足構造があります。更に、投機筋の介在が状況を複雑なものにしているわけです。
中長期のウィンウィン方針なしでは先へ進めないコメ問題
そんな中で、日系アメリカ系の国府田ファームなどが苦労して作ったにもかかわらず、長年日本が食用輸入を拒んできた中粒米(カルローズなど)が、日本で本格的に流通し始めています。外食チェーンなどでは導入は始まっており、このままですと日本人の一般家庭の食卓でも中粒米が主流になるかもしれません。反対に、最高の食味を誇る短粒米(ジャポニカ米)の良品は、国内の高級料亭向け以外は輸出に回って貴重品になるかもしれないのです。
クールジャパンなどと威勢のいいことを言って、日本の食文化を宣伝した結果、その価値が国際社会に「バレて」しまい、先進国経済の価格形成プロセスに引っ張りこまれてしまいました。その一方で、日本国内は相変わらず生産性が低く、高度知的産業が育たない中で、経済成長が進まず、家計の消費パワーは伸びていません。その結果として、主食のコメですら良品については「日本のコメを日本の消費者が買い負ける」という悲しい展開になりつつあるわけです。
まず、このコメ問題については、この全体像の認識が必要です。ですが、こんな複雑な話は世論に対して説明するにはよほどのスキルがないと無理。それに、選挙区別に見ていけば、コメの場合は消費地と生産地で利害は正反対になります。特に前回の参院選では、消費地向けに訴えた米価引き下げ政策が、生産地では嫌われて自民党は大敗してしまいました。
では、その張本人である小泉農水相を首班に選ばず、改めて生産地に媚びた米価上昇追認を打ち出したら、自分党は勝てるのかというと、その場合は消費地では惨敗するかもしれません。いやいや、両方の票がほしいというのであれば、コメ問題は争点にできないことになります。
そして野党の場合は、迷走する自民党を叩けばいいのですから、実にゲームでポイントを取るのは簡単です。ですが、構図としては無責任極まりません。では、消費地も生産地もウィンウィンになるようにするには、どうしたらいいのかというと、より一層の大規模化を進めるしかないわけです。
政策としては、それしかないのですが、大規模化を進めると小規模な兼業農家が猛反発します。ですから、基本的には争点にはできないことになります。そして、総裁選に勝って内閣を作れば、結局は袋叩きのサンドバッグになるだけです。
例えばですが、小泉氏の場合は農業改革に取り組んだ実績を背景に、一気に「大規模化」を訴えて正面突破ができるのか、あるいは専門家なりに巧妙に「利害相反から逃げて、言葉のゲームでごまかすのか」ということになると思います。
例えば高市氏の場合は、適当にごまかしながら、それこそ「生産地の小規模兼業農家」の中に一定数はある「保守イデオロギー」という飴玉を配りながら、時間稼ぎをするということになるのだと思います。
いずれにしても、どんな政権ができても、コメの問題は中長期のウィンウィン方針がなければ、先へは進めないわけです。かといって、仮に大規模化へ突き進むと、地方票を敵に回すだけでなく、都市部でも「有機農法の小規模な農家のブランド米がいいな」などという新興保守政党が邪魔をする中で、本当に無理ゲーをどう突破するかという話になります。
もはやかなりの「無理ゲー」になっている物価対策
もう一つの物価対策も、かなりの無理ゲーになっています。現在の物価高は、まずエネルギーコストの上昇があり、そこに人件費アップが乗っています。これは日本だけでなく、全世界的なトレンドですから、例えば建設資材とか輸入穀物などの場合は、そうした世界の物価高に、円安効果が乗っかって大変な事になっているわけです。
では、日本の場合は賃金を抑制すればいいのかというと、さすがに「現時点での賃金は安すぎる」ので、賃金は上げて国内消費を増やす政策は必要ということで、これはある程度の合意が取れていると思います。問題は円安です。円安はかなり危険水域にはいっており、このままですと国民生活が破綻します。
その一方で、米国の景気は「もしかしたら」スローダウンしているのかもしれず、これを過大に考えるトランプ政権は「利下げ」を強く主張しています。連銀がもしも、これに屈して利下げをしますと、日米の金利差は縮まって、日本円には円高圧力が生じます。そうなれば、原油をはじめとして、日本から見た輸入品の物価は下がるので、物価問題としては一息つきます。
ですが、もしかすると日本円に対する世界の市場の評価は、「日本経済の実力」が地盤沈下する中では、そうは簡単に円高には振れないかもしれません。反対に円安が加速するということも想定しないといけません。仮にこれ以上の勢いで円安が加速すると、石油も小麦も、そして喫緊の課題である建設資材なども更に一段高騰することになります。そうすると、日本の国内経済は激しく動揺します。
では、日本の方も金利を少し上げて調整と行きたいところですが、国家債務が天文学的な現状では、僅かな金利引き上げでも、国債の利払いが拡大することとなり、事実上借金が複利で膨張していきます。
その一方で、現在の日本経済の中で「リッチなグループ」、つまり日本発の多国籍企業である成功しているメーカー、金融、商社、その従業員、そして株に投資しているグループなどは、圧倒的に円安を好みます。売上利益の過半は海外で稼ぐ中で、その反映である利益なり、株価が「円に倒すと」膨張するからです。
現在の日本ではそのように、ドルベースの勝ち組と、純粋国内経済の負け組に分けられ、格差が拡大しています。ちなみに、インバウンドで潤う観光産業などは前者にカウントされます。反対に、後者の場合は年々縮小する国内経済、その一方で円安で暴騰する原料、資材、エネルギーコストを食らっています。そんな中で、自公政権という現体制はどうしても前者の利益代表という側面を否定できないわけであり、一定程度の円安を志向することになります。
というわけで、円安が物価高の大きな要因である中でも、国としては円高政策は取れません。そんな中で、物価対策をするにしても、「円高シフト」という根本的な対策は取れないわけで、そうすると国民の生活水準を守るには「給付」または「減税」という対策にならざるを得ません。
麻生も森山も「自暴自棄」に陥っているのが事実か
ですが、一過性の給付にしても、恒久的な減税にしても、財政規律には反します。つまり国家の債務を増やす政策です。そうなれば、日本の財政は「A地点」に接近する可能性が出てきます。それは、巨額の国家債務を国内で消化できずに、国際市場から資金調達をしないといけなくなる地点です。
このAに到達すると、程なくしてB地点がやってきます。それは「金利を上げないと国債が消化できないが、金利を上げると国債価格は下がり、円も下がる」という現象が始まる地点です。つまり、高金利による貨幣価値の毀損が始まるわけで、これはイコール「悪性インフレ」のスタートになります。そこから先は、どんどん日本のアルゼンチン化が加速していき、C地点に至ります。
そのC地点というのは、資産の海外逃避が始まるポイントです。そして、その先に待っているのは、国債の支払い不履行、つまり国家の破綻ということになります。現時点の日本はまだ大きな経済規模を持っていますので、仮に国債の支払いが不履行になっても、IMFなどが乗り出すことはできません。日本経済は「大きすぎて破綻させると、地球上の経済全体が大被害を受ける」からです。
ですが、仮に円が十分に安くなり、GDPが相当に縮小してくると、破綻が可能になっていきます。とりあえず、その時点では日本国内の経済秩序も、社会秩序も相当に崩壊している可能性があります。いずれにしても、B地点からC地点になると、国民の生活水準は大きく損なわれ、物価高に加えて品不足も顕著になるでしょう。その前に、根本的な手を打って、破綻へ向かうシナリオを食い止める必要があります。
現在の減税論議、給付論議にはこの点が決定的に欠けています。今回の政変では、森山氏の影響力と麻生氏の影響力が力比べをしているというデッサンがされています。ですが、この両氏ほどの人物となれば、日本がA地点を超えてB、そしてCへ向かうことへの恐怖と、それを回避することへの責任感を感じているのは間違いないと思います。
ですが、同時に麻生氏も森山氏も「今の世論に対しては財政規律などという難しいことを言っても理解してもらえない」という自暴自棄に陥っているのも事実だと思います。それでは、ダメなのです。また、野党各党も有権者に媚びるのは得意でも、この種の説明をするだけの気迫のある政治家は皆無だと思います。
そんな中で、自民党は少なくとも「財政規律」は意識しています。ですから、恒久的な歳入低下を招く減税ではなく、一過性の給付を志向しているわけです。その延長で、次期政権はいったい何をどのように国民と対話していくのか、これは大きなハードルになります。
簡単に整理しますと、コメと物価対策というのは、一刻を争う急務です。この2つの課題に対して、どのような対処するのかということは、失敗すれば一発で政権が吹っ飛ぶ中での大きな試金石になると思います。
パラドックス的な党内で「求心力」を作れるかという問題
2番目の観点は、イデオロギー問題です。日本の場合は、前回の参院選で右派のポピュリズムが一気に加速しましたが、これはあくまで、タレント議員が知名度で票を稼ぐのと同じです。どうでもいい感情論に根ざしたポピュリズムで、票を稼ごうというのですから、無責任極まりません。もっとも無責任というのは左派も同様です。
ですが、自民党内の場合は少し様子が違います。例えば、現在のイデオロギー上の大きなテーマであるのは、中国との外交と、外国人への排外感情です。その場合に、自民党の政治家としては、選択できる政策には幅はありません。自民党には保守派というのがいて、これはテクニカルに2種類のグループに分けられます。
第一は組織票が弱いので、都市部の右派浮動票をかき集める必要のある議員です。ネトウヨに受けるようなパフォーマンスを繰り返しているのはこのグループです。第二のグループは、既得権益を抱えた支持層に対して、支持を固めるために右派のイデオロギーを使っているグループで、これは地方選挙区に多いわけです。
前者は永遠に実行不可能なファンタジー的な右派言説を垂れ流す必要があるグループですが、後者の場合は、ある程度の満足を支持者に与えれば、票は囲い込めるというグループです。この後者、つまり利権誘導型の選挙区を勝ってきた政治家の場合は、ビッグネームであればあるほど、「今の時代には利権誘導はできない」一方で「人畜無害な右派イデオロギーを見せることはできる」その上で「国を代表した実現可能な政策を選択」していくわけです。
安倍晋三氏が一番いい例で、利益誘導はできない中で、右派的なパフォーマンスはする、けれども実際の政策は実現可能なゾーンの内側で、場合によっては中道左派的な政策も実行したわけです。
この安倍氏の例が示しているのは、選挙区は保守、これまでのパフォーマンスは保守、けれども政策は実行可能な範囲で、中道左派の政策も進める、という複雑な立場を取った場合に、比較的政権は安定するということです。
安倍氏の場合は、右派のイデオロギーをパフォーマンスで見せても、それでも足りない分は、秘書などが「桜を見る会」的なエサ撒きを止められなかったわけです。それぐらいに、利益誘導はもうできなくなっているし、既得権の保護も限界に来ているわけです。そんな中で、弁当や観劇、旅費といった餌に加えて、右派のイデオロギーという「エンタメ」を見せて、辛うじて支持者を繋ぎ止めているということだと思います。
裏返して考えると、日頃から選挙区がニュートラルもしくは、多少に都市型で、リベラルな言説で売っていた政治家の場合は、総理総裁になって地方票と向き合う場合には、「突然右派的になってパフォーマンス」をする必要があったわけです。石破氏の場合は、その芸当に乗らず、なおかつ米価の問題で地方票を敵に回したことが命取りになったのだと思います。
今回の政局に対して考えるべきなのは、例えば小泉、高市、林、小林といった面々が、どの程度こうしたパラドックス的な自民党の中で、求心力を作れるかという問題です。
高市、小林といった保守パフォーマンスで売っている政治家の場合に、保守的な地盤を引っ張りながら、最終的には実現可能な政策のゾーン内で社会を先に進めるのかが問われます。
保守的な地盤でありながら、中道左派的な言動が許されている林芳正氏の場合は、少し逆で、もしかしたら利益誘導的な活動、あるいは人脈的なものを基盤にしているのかもしれません。また日頃は中道左派的な言動をしていたというイメージが強すぎると、総理になったら保守的な言動に振らざるを得なかったりします。
いずれにしても、保守的な人がなれば政策が保守的になる、中道左派的な人物であれば政策もそうなるかというと、じつは反対の力学が作用すると見なくてはなりません。
一番奥にある大事な「中の人の実力」という要素
3番目として、一番奥にある大事な要素というのは、やはり首班の「中の人」の実力です。具体的には2つあり、何よりも政策に関する理解度が重要です。世論のリテラシーを低く見て、思い切り簡素化して言うにしても、あるいは面倒なことを丁寧に説明するにしても、問題点が理解でき、有権者に売り込む政策を巧妙に説明できる能力がなければダメです。
今回は特に、コメと物価について、政権を担う以上はマトモに喋れなくては、一発で政権は崩壊すると思わなくてはなりません。
もう一つは外交です。首脳同士の信頼関係というのは、何もそんなに高度なことが要求されるわけではありません。日本国には外交方針があり、局面に応じて総理が行う外交には方向性も裏付けもあります。それを理解して、あとは国際的な社交のイロハを間違えなければ、前へ進むことはできます。
ですが、この種のコミュニケーションについて、全く不向きな人がなると、これは本人も周囲も苦しむことになります。周囲のブレーンを含めて、国内向けにも国際的な外交の世界でも「コミュニケーションの軸」として機能する「マシン」となれるのか、これが最終的には大きな要素になると思います。
整理しますと、コメと物価を中心とした喫緊の課題に関する解決力、そしてイデオロギーをメッセージとしながら政策を実現可能なゾーン内に入れる政治勘、そして「中の人」の素のコミュニケーション・スキル、という3層。これで候補一人一人を見ていくことになると思います。
振り返りますと、官房長官として、あれほど政策と政治に精通していたと思われた菅義偉氏も、国民との対話力としてはほぼゼロに近かったわけです。また、外相として、ベテラン議員として知性も能力もあると思われていた岸田文雄氏も、中の人の知性や判断力は全く平凡であったわけです。
そして、今回の石破氏もそうです。巨大な現状不満が吹き荒れる中で、選挙に勝つだけの対話力はやはり全く不合格でした。この3人の例を考え、更に若き日の麻生太郎氏の失敗、福田康夫氏の無責任などを総合した場合に、トータルの印象として浮かび上がるのは、やはり不安感です。
今回の、小泉進次郎、高市早苗、小林鷹之、林芳正、茂木敏充、といった顔ぶれの中で、誰か、こうしたハードルを超えられる人材がいるのかどうか、どうにもこうにも不安が残ります。まずは、コメと物価そして財政規律について、徹底した討論をやって、その中でパフォーマンスを評価してゆくことが必要ではないかと思われます。
image by: oasis2me / Shutterstock.com
MAG2 NEWS

 1 ヶ月前
12
1 ヶ月前
12



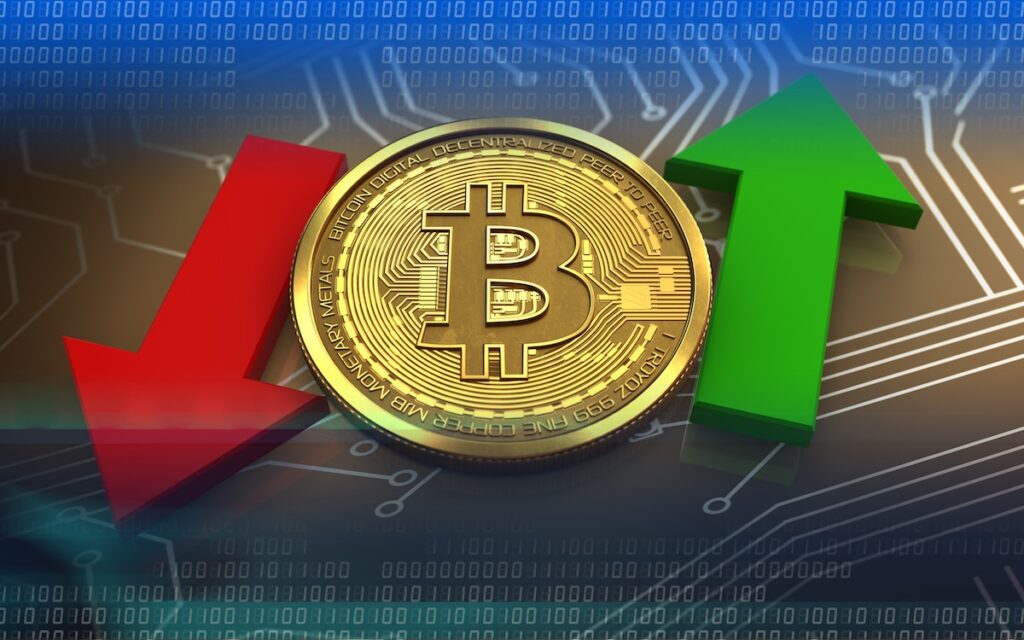

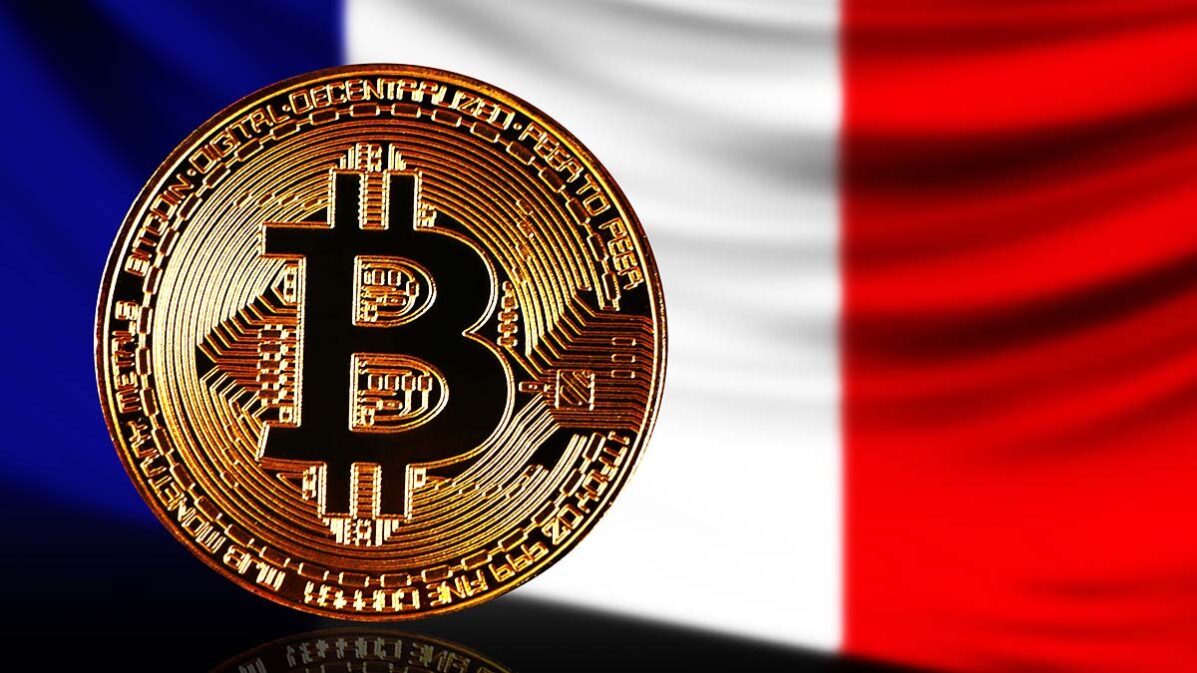


 English (US) ·
English (US) ·  Japanese (JP) ·
Japanese (JP) ·