
旧安倍派を中心に自民党内で高まる「石破おろし」の声をよそに、続投のスタンスを崩さない石破氏。一部からは意固地とも揶揄される姿勢は、どのような意図により支えられているのでしょうか。今回のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』では元全国紙社会部記者の新 恭さんが、考えうる2つの背景を紹介し詳しく解説。さらに去就が取り沙汰されている森山幹事長の「腹積もり」を推察しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:旧安倍派主導の政権を阻止するという「石破続投」もう一つの狙い
旧安倍派主導の政権阻止だけではない。石破氏が「続投」にこだわるもう一つの狙い
「(石破首相は)進退問題については森山幹事長に委ねていると思います」
石破首相の「指南役」といわれる山崎拓氏(元自民党副総裁)は、21日の「報道1930」(BS-TBS)にVTR出演し、そう語った。
「続投」姿勢を崩さない石破首相に対し、自民党の森山幹事長がどう考えているのかは現在の政局を占ううえでの重要なポイントだ。“国対族”として与野党を問わず幅広い人脈を有し、党内のまとめ役としての能力も高い森山氏が、その方面を苦手とする石破首相にとって、政権運営の要石であるのは間違いない。
森山氏は7月28日の両院議員懇談会で、「参院選の総括をする報告書がまとまった段階で、幹事長としての責任について明らかにしたい」と述べている。これをメディアが勝手に「辞任する」と受け取って報道しているのだが、そんなことになれば、石破政権はとてもやっていけない。
そこで、森山幹事長は自ら退くことによって、石破首相を引きずり降ろそうと考えているのではないかと見る専門家がいるわけである。しかし、少なくとも山崎氏はそう思っていない。進退を森山幹事長に委ねているというのは、森山氏の言う通りにするという意味ではなく、「続投」のための策を練れということだろう。山崎氏は語る。
「たぶん、あと2年やって、その時に誰にバトンタッチするか考えると思います」
山崎氏は昨年5月、小泉純一郎元首相らとの会食に、「ポスト岸田」の有力候補だった石破氏を招き総裁選への出馬を促した。その後も交流を続け、今月24日夜に再び、同じメンバーで会食している。石破首相の思いを最も理解している人物の一人といえるだろう。
その山崎氏の次の発言内容も示唆に富んでいる。石破首相が「いちばんやりたいこと」は何かという問いへの回答だ。
「“2027年問題”だと思う。台湾有事の可能性がいちばん高まるのが、2027年と言われている。何としても(台湾有事を)阻止したいのが、本当の思惑です」
石破首相はトランプ関税をめぐる日米交渉などを表向きの続投理由にあげるが、真の狙いは「台湾有事の阻止」にあるというのだ。となれば、俄然、話はキナ臭くなる。
石破首相は現実的な安全保障論者でありながら、無分別な武力行使には慎重な姿勢を示してきた。安倍晋三元首相が「台湾有事は日本の有事だ」と述べ、台湾有事の際には一定の関与を行う可能性を示唆したのに対し、石破氏は台湾有事を「少なくとも重要影響事態だ」としながらも、自衛隊の出動には抑制的な考えであり続けた。
山崎氏の言う「台湾有事の阻止」は、台湾における一触即発の危機において、自衛隊を安易に参戦させるような“タカ派政権”の誕生を阻止するという意味が濃密に含まれていると見るべきだろう。
誰も文句のつけようがない森山幹事長の「老獪な危機管理」
石破氏は自らを「保守リベラル」と称し、リベラルの本質は寛容性にあるとしている。少数意見を大切にし、野党にも丁寧に耳を傾ける態度こそが「保守」の本質であると説いている。この理念は、特定のイデオロギーを前面に出す「強硬保守」の政治スタイルとは根本的に異なる。
昨年の衆院選や今年の参院選での惨敗は、石破政権にとって大きな痛手ではあった。だが、安倍派を中心とする自民党内の「強硬保守」勢力が後退し、相対的に穏健派の発言力が増す政治的環境が整ったことをプラス面と判断、それを持続させるために「続投」を宣言し、高市早苗氏ら保守強硬派に台頭の機会を与える「総裁選」を容易に開かせないよう画策している可能性がある。
そもそも石破首相には、選挙で負け続けている原因が裏金問題や統一教会問題を引き起こした旧安倍派にあり、そのメンバーを軸とした保守系議員たちが「石破おろし」を主導しているのは許せないという思いが強い。だからこそ意固地になって政権にしがみついている側面もあるのだろう。
むろん、その意向を支える政治的歯車として、見逃せないのが森山幹事長であり、その動きだ。参院選後、党内から石破首相の退陣を要求し、両院議員総会の開催を求める署名活動が活発化したさい、「党則に則って判断する」という誰も文句のつけようがない方針を示したことは、老獪な「危機管理」といえた。
その方針は、両院議員総会でも適用された。保守派と目される有村治子氏が総会長として議長をつとめ、総裁選の実施を迫る“アンチ石破”議員の意向を汲んで参加者にこう提案した。
「党則に基づき、臨時総裁選を行うかどうかの意見集約を党の総裁選挙管理委員会にやってもらうよう申し入れる、ということでよろしいですか」
そのさい、有村氏に発言を促された森山幹事長は「ルールに基づいて運営することが大事だ」と念を押して、そのまとめ方に賛意を表明。提案はスムーズに了承された。
これで、総裁選に向けて急ピッチで動き出したかのごとくメディアは報じたが、「党則順守」という厳格かつ公平なイメージが思わぬ方向に働いた。
8月19日、総裁選挙管理委員会の初会合。終了後、記者団の前に姿を見せた委員長、逢沢一郎衆院議員はこう語った。
「厳正に慎重に制度設計をして間違いのない意思確認を行っていく」
参加者の話によると、総裁選のように全員が集まって無記名で投票すべきという声も上がったが、逢沢委員長は「総裁の地位にかかわることで、厳正にやらねばならない。誰が書いたのかわからない投票は好ましくない」と述べたといい、記名回答になる可能性が高まっているようだ。
記名となれば、石破政権が存続した場合の人事上の不利益を懸念する心理が働くだろう。ただでさえ官邸や党本部への“忖度”で生きながらえている議員の多い自民党のことだ。反石破の急先鋒はともかく、副大臣や政務官、党の役職についている議員たちは、役職を辞めない限り総裁選開催に賛成しにくくなる。
石破退陣を求める議員に対して心理的圧力をかけるやり方ともいえるが、「厳正な判断」という大義名分が立つため、反石破派が正面切って反対できないのは確かだろう。
援軍を得て「計略通り」に事を進めた森山幹事長の進退
森山氏を側面から応援しているのは、鈴木宗男参院議員だ。今年6月、23年ぶりに自民党に復党した鈴木氏は、叩き上げで幹事長までにのしあがった森山氏とは長い交流関係がある。平成10年の参院選に、鹿児島市議だった森山氏が出馬したさい、当時の橋本内閣で閣僚をつとめていた鈴木氏が支援して、当選に導いた。昨年9月の鈴木氏のブログには「幹事長に森山裕総務会長が就任するのは見事な判断である」と石破首相を持ち上げる記事が掲載されている。
7月28日の両院議員懇談会で、鈴木氏は「総裁選の前に、まずは参院選で負けた総括をすべきだ」と発言。その後、「派閥パーティー収入不記載事件に関与した議員に対し、再再度処分すべき」という主張を繰り返している。
鈴木氏はこう言いたいのだろう。裏金議員が総裁選をやって総理・総裁の顔をすげ替えよと騒いでいるが、彼らの不記載事件こそ選挙結果に響いてきたことを思い返し、党はあらためて国民の納得が得られる処分をするべきだ、と。
鈴木氏ら石破擁護派の発言がメディアに取り上げられるごとに、安倍派を中心とする裏金議員が「石破おろし」に暗躍しているというイメージが広まり、世論の風向きが「石破続投」を容認する方向に変わってきた。総理交代への期待は急速にしぼみ、総裁選挙管理委員会が「記名回答」や「氏名公表」を選択するなら、総裁選見送りの可能性が高くなりそうだ。
いまのところ森山幹事長の計略通りに進んでいるように見えるが、自身の進退についてはどうするつもりなのだろうか。
そもそも森山幹事長に辞任のインセンティブがあるとは思えない。石破首相に義理や愛着などないにせよ、世論の動向に反してまでこの政権を潰したくはあるまい。だが問題は、自ら「幹事長としての責任を明らかにする」と辞任を匂わせて、いったん参院選直後の急進的ムードを落ち着かせたことだ。なのに、そのまま留任するとなれば、「潔くない」と反発する声も出るだろう。
それでも、森山氏は幹事長に留まるのではないかという気がする。たとえ反石破派を懐柔するために幹事長ポストを明け渡すとしても、幹事長代行や代理として実質的な幹事長の仕事を続ける腹積もりなのではないか。
おそらく、森山氏は「ポスト石破」として小泉進次郎氏を思い描き、そこまで党の中枢部に居続けたいだろう。進次郎政権になれば、その“経験不足”を補って、縦横自在に立ち回れるはずだ。
総裁選は行われず、石破首相はしばし続投。野党第一党の立憲民主党が、あたかも大連立のごとく裏で支える。そんな可能性が高まってきた。しかし、それが国民にとって幸せなことかどうか、疑念は大きく膨らむ。財務省に操られ、「増税」路線から抜けられない古ぼけた政党どうしのエセ対立構図を延々と見せられ続けることに国民は倦み疲れている。
新 恭さんの最近の記事
- 進次郎でも高市でもない。“キングメーカー復活”を虎視眈々と窺う麻生が担ぎ出しかねない「茂木敏充」の致命的な欠陥
- 米公文書が裏付けた「CIAが自民党に秘密資金援助」の事実。アメリカ側に“隠蔽”を懇願していた大物政治家の実名
- 橋下徹氏の驚くべき“暴露”。「進次郎総裁なら自民と維新の連立も可能」発言に含まれた重要なメッセージ
- 「トランプに屈して80兆円を献上した売国奴」のレッテルは絶対に貼られたくない。石破茂が“首相続投”にこだわる真の理由
- 進次郎でも高市でも無理。参院選で大敗しても首相の座にしがみつく石破が描いた仰天の“裏シナリオ”
image by: 石破 茂 - Home | Facebook
MAG2 NEWS

 1 ヶ月前
17
1 ヶ月前
17



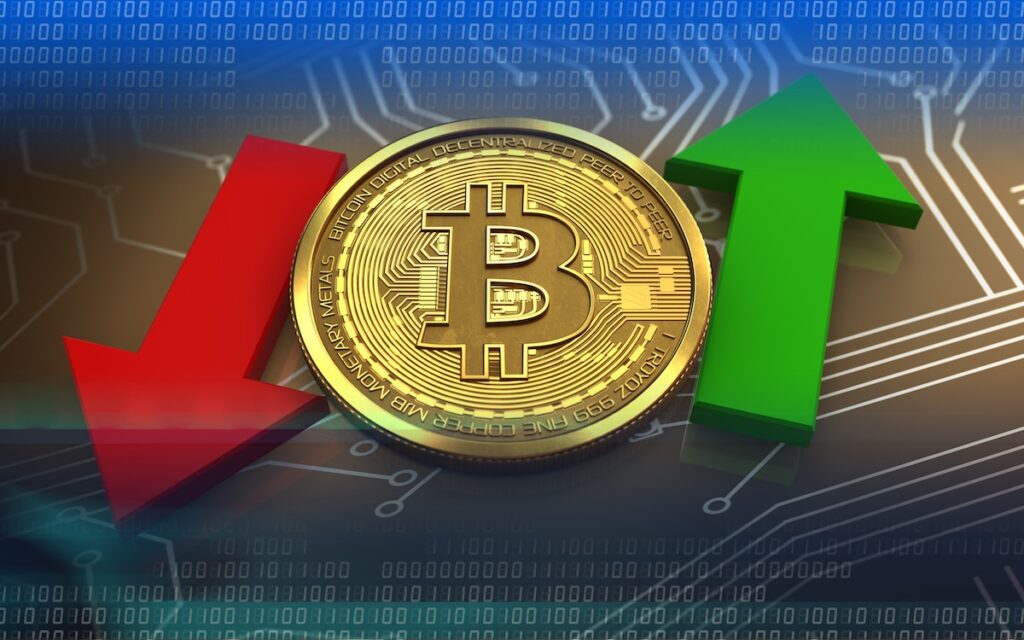

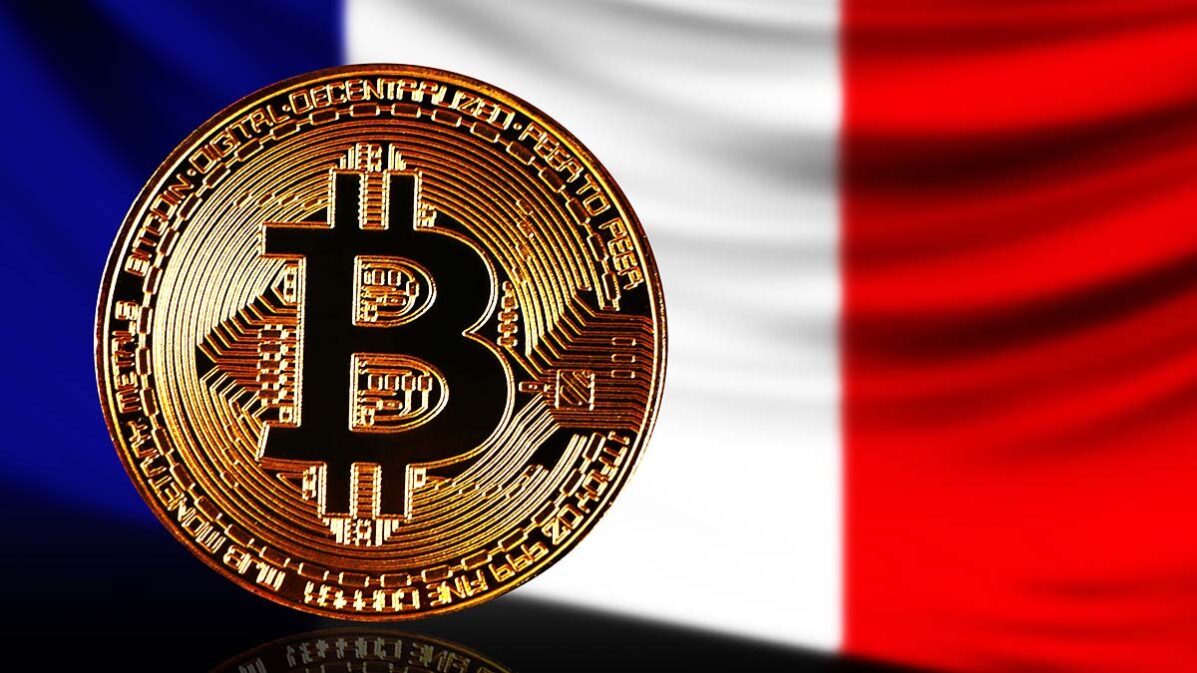


 English (US) ·
English (US) ·  Japanese (JP) ·
Japanese (JP) ·