
「石破おろし」を巡る自民党内と国民感情のズレに象徴されるように、混迷極まる我が国の政治状況。その原因は一体どこにあるのでしょうか。今回のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』では作家で米国在住の冷泉彰彦さんが、3つの観点から「日本政治の行き詰まりの構造」を考察。その上で、何が一番の問題であるかを明らかにしています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:日本政治における行き詰まりの構造
こんな日本に誰がした。国内政治「どん詰まり」の構造
石破総理は現時点では、衆院選で敗北し、参院選でも敗北したことから、自民党内で「石破おろし」が発生。総裁選の前倒しが叫ばれていたのですが、お盆明けの状況としては徐々にこの声が小さくなっています。世論における石破総理の支持が回復している中で、「石破おろし」の勢いが弱くなっているのです。
では政局はこれから安定してゆくのかというと、そうではないと思います。依然として、と言いますか今回の参院選以降としては、前代未聞とも言えますが衆院でも参院でも少数与党が続く中では、石破政権はいつ崩壊してもおかしくありません。政局の安定というのは、あり得ないと思います。
一言で言えば、日本の政治が行き詰まっているということです。今回はその「行き詰まり」がどこでどのように起きているのか考えてみることにします。大きく分けて3つ指摘できるように思います。
1つは、自民党内の勢力関係の問題です。今回、参院選後に「石破おろし」を叫んだのは清和会系の、つまり旧安倍派の面々が主でした。その勢いがなくなったのには、前述のように石破氏の人気回復という動きがあります。同時に世論の中にあったのは、「党内保守派というのは旧安倍派、つまり裏金議員ではないか」という声でした。
これは興味深いのですが、前世紀までのネットのない時代というのは、政界などでスキャンダルが起きても、いつの間にかTVや新聞が取り上げなくなるということが良くありました。そうしてTVと新聞が取り上げなくなると、いつのまにか世論も昔のスキャンダルを忘れるという格好になったのです。
具体的には、スキャンダルが出ても、その後の選挙で当選してきたら「みそぎ」が終わったという感覚がありました。政治家本人もそんな感じで復権したような態度となり、メディアも昔の話を蒸し返さない雰囲気がありました。ですが、現在のネット世論というのはネガティブ情報はいつまでも覚えているのです。
世論の心理的な変化もあると思いますが、ネット記事というのもが意外と長期間アップされているし、転載されたり魚拓化されたりするものを含めると、ほぼ永久に検索に引っかかるというのが大きいと思います。昔なら考えられなかったような詳細な政治家の経歴がウィキなどで簡単に見られるのも大きいと思います。
ですから、保守派による「石破おろし」についても、「結局多くは裏金議員じゃないか」という指摘がネットでされてしまうということになったのでした。
では、これで自民党内は「保守派」ではなく石破氏を代表とする中道の覇権が確立して、少なくとも党内が安定するのかというと、必ずしもそうとは言えないと思います。
今回の参院選で顕著となったのは、単に「自民党内保守派」の票が「保守野党」に流れたというだけではありません。かなり複雑な問題が、そもそも自民党なるものを空中分解の危険に追い詰めているとも言えます。
全国的に「保守票」が保守系野党に流れた根本的な理由
例えば今回、どうして全国的に「保守票」が保守系野党に流れたのかというと、その根本の部分には組織の弱さということがあると思います。
例えばですが、安倍晋三氏の「桜を見る会事件」や、小渕優子氏の「ドリル優子事件」がいい例です。仮に安倍氏や小渕氏の「選挙の強さ」というのがホンモノなら、有権者が「安いカネで桜を見る会に招待しろ」とか「貸切バスでの芝居見物に招待しろ」といった「タカリ=収賄」行動に走り、それに屈するということはなかったと思います。
では、どうしてそんなに組織力が弱くなったのかというと、インフラを中心としたバラマキは既にほぼ完了しており、更に新規は財源難で難しいからです。また補助金行政も、ネット世論などの目が光っているので困難です。その一方で、地方名望家の保守イデオロギーというのも、実態はそんなに信念があるわけでもないのです。
安倍氏の場合に、総理として頑張っている人を、自分の選挙区から送り出しているだけで満足できないというのが、そもそも奇妙です。また、安倍氏が、その人気を逆手に取って、ゴリゴリの保守が反対しそうな「日韓合意」「譲位改元」「相互献花外交」などをやっても、あまり反対しなかったというのは、保守理念がホンモノではなく、単にリベラル野党を「やっつけるのが快感」という域を出なかったのだと思います。
考えてみれば、安倍氏の「桜」問題というのは、実は清和会全体の裏金問題の典型だったと考えることもできます。地方の各選挙区では、どうしてもこの種の支持者による「タカリ構造」があるし、そこに資金を入れないと当選できない、だから次期リーダーを目指す議員は派閥内の派閥を強化するにはカネをばらまくしかない、そういった構図です。
今回の参院選で彼らの多くが苦戦したのは、勿論、これ以上のバラマキができないということもありますが、裏金スキャンダルが暴露されたために、本当に裏金が回ってこなかったからなのかもしれません。地方の保守票までが安易に保守野党に変節した背景にはそうした問題もあるように思います。
もっと言えば、都市の保守野党人気は一種のネトウヨ的な右のポピュリズムの体現だったのだと思いますが、地方の保守票まで動いたのは、カネの切れ目が縁の切れ目的なおかしな構図があったのかもしれません。仮にそうした「腐敗しているのは有権者」という構造があるのなら、そのような風土を持つ選挙区は衰退しても仕方がないとも言えます。
自民党は都市部でも苦戦しましたが、1つの要因としては組織票の縮小ということが大きいと思います。保守系の商工団体は青息吐息で、彼らにバラまく補助金の財源もないのでケアができなくなっています。
大きな要素としては、団塊世代までは巨大な基礎票を形成していた宗教票がどんどん「溶解」しているのだと思います。組織力の強い宗教は、現在の現役世代には全くもって「コスパが話にならない」中では組織力が衰退、それが自公の集票力低下につながっています。
組織票と言えば、前世紀までは企業の組織票がありましたが、これも完全に時代錯誤ということになりました。
というわけで、自公政権の基礎票というのが、かなり深いところで溶解しているわけです。これに、米政策の迷走による消費者と生産者双方の不満感、そして物価高への不満、長期間の経済低迷の責任論などが大きく重なって今回の結果になったと考えられます。
「政権担当の責任から逃げ回る」という保守野党の問題点
2つ目は、保守野党の問題です。維新、国民、参政と、それぞれに性格は異なりますが、彼らに関しては共通の問題点があります。それは、フルセットの全国政党でないということ、そして政権担当の責任から逃げ回るというビジネスモデルだということです。
まず維新の場合ですが、結局のところは大阪の「アンチ東京、アンチ自民、納税者の反乱」というコンセプトだけが残っています。全国的には「旧みんなの党」的な歳出カットのコンセプトでは党勢が獲得できなかったわけです。成長戦略だとして、IRとその立地の土地改良で万博をやったことが「浪費」イメージを拡散したのが衰退要因です。
ですが、多少なりとも外交や安全保障に関心のあった橋下氏がリタイアした後は、そうした国全体の問題には無関心な人材しか残っていない感じもあります。それから、強烈に「納税者の反乱」的な「小さな政府論」を掲げている中では、日本の地方をどうするのかという大問題は放置するしかないわけで、結局は地域政党を脱皮できない構造にあります。
国民民主党は、元来が「希望の党」崩れであって、元の大きな民主党から改憲派が分かれたのがルーツです。ですから、自民党などとは政策的な相性は良いはずですが、「穏健野党で、手取りにこだわる」というコンセプトが何気に都市の中間層に刺さる中では、「穏健な現状不満の受け皿」という立ち位置が十分に商売になることが証明されてしまいました。
例えばですが、玉木首班、榛葉官房長官というような人事を担いで、自公が「村山内閣方式」でフル連立に取り込むという可能性は自公の側からはあるわけです。ですが、その方式では解散総選挙をしたら、自公と共に「有権者の現状不満のターゲット」にされるのはミエミエであり、その場合はこれまでの蓄積を相当に失うでしょう。
国民民主党は、そのことを痛いほどわかっているのだと思います。それ自体は冷静で現実的な判断力を示していると思いますが、同時にこれは究極の無責任だとも思います。
参政党に関しては、非常に原始的な右派ポピュリズムを票にするというテクニカルな実験政党で、それ以上でも以下でもないと思います。特に都市の現状不満票を掘り起こしたのは、100%否定するべきでもないと考えています。同時に、この先に国会内で活動する際には、個々の法案や予算案に対して最終的には有権者の期待に応えるような「判断の軸」を示すことは難しいでしょうし、賞味期限は存外短いのではと見ています。
一部には旧日本新党のように、参政党が「通常では政治家に進むことはなかった人材を発掘」する効果はあるのではという声があります。ですが、この点については見回したところ、そもそもの「タマ」がそこまでのレベルではないと思われ、そうした効果も限定的だと思います。
ただ、そのように稚拙な実験ではあっても、十分に「野党であるメリット」の「うま味」は理解しているようで、国民民主と同様に次回の衆院選でも、「現状不満の受け皿」というビジネスモデルで、ある程度の議席は取るのでしょう。
メインの支持者は「逃げ切り世代の富裕層」の立憲と共産
3つ目は左派政党群についてです。アメリカ民主党における「オバマ=ヒラリー路線」が大破綻に至ったように、人権や多様性を中心としたイデオロギーを掲げるものの、主要なマーケットは富裕層だという「21世紀初頭型のリベラル運動」というのは、完全に時代遅れになっています。
にもかかわらず、立憲も共産もそうですが、ご本人たちは「大企業や富裕層は批判する」という立場だというセルフイメージを持っていても、実際のところはメインの支持層は過去世代、イコール逃げ切り世代の富裕層になっています。共産党などは「違う」と強弁するでしょうが、実態は新聞代や党費を払える層が中心というだけで、現代ではやはり「持てる層、逃げ切れる層」の党ということになると思います。
問題は、左派思想というのは本質的な問題として、「持たざる層」つまり経済的に不安定な層の利害を代表して正義にしないと、成立しないということです。アメリカの場合は、それでも「最貧困層には再分配をする」という姿勢はありました。それでも中の下など「取られるだけの層」がイデオロギー的に中道左派を憎悪するようになると、ビジネスモデルの全体が崩れてしまったのです。
そう考えると、最貧困層への再分配ということでは、立憲も共産も全くもって冷淡です。そもそもが教育水準が高く、従って富裕層であるが「戦後的な正義」にこだわる層が、立憲のコア支持者です。共産の場合はカネを出して組織を支えると見返りがあるという互助組織に近いわけで、どちらも最貧困層への強い再分配を志向していません。それどころか、世代的な限界が大きく、現在の若年層の社会苦への理解も薄いようです。
共産の場合は、党首が交代したことで「共産党が政権を取ったとして、すぐには資本主義を停止しません」などとバカ正直な「理念の解説」を始めています。どうやら本気で21世紀の今日に、世界中で失敗した計画経済を「すぐにではないが、後で」やるらしいので、基本は通常の有権者は「ドン引き」になると思いますから、基本的には論外の存在だと思います。
問題は立憲です。とにかく政権担当をしていた時代から、政策のセンスが全く地に足がついていません。有期契約の労働者を救おうとして無期(終身雇用)転換の制度を作ったら、結局は派遣切りが横行するだけといった感じで、とにかく「現場の声と利害を代弁」できていません。
そんな中では、左派政党の潜在支持票の行き場は「れいわ」ぐらいしかないわけです。ですが、「れいわ」の政策パッケージが現実と重ならないのは、参政党と同じです。失われた昭和のストーリーを亡霊のように復活させたいというファンタジーの描き方もソックリです。何しろ、経済政策の最初に書かれているのが、中小企業の数を減らさないというのですからドン引きです。
中小企業が多いのは、オーナーがチマチマした搾取をやり、労働者は劣悪な条件で働かされ、結果として薄利多売の競争力があるという絶望的な構図があるからです。自動車産業で言えば、エンジン組み立てという複雑な工程は中国の生産性に取られてしまっています。結果的に残っているのが鋳型とかネジといった低付加価値産業だけで、それは日本がアジア諸国より生産性がいい、つまりは労働者が不当に搾取されているからです。
全体的に見て事実上「崩壊寸前」の日本の政治風土
面白いのは、この主張は参政党の「アトキンソンは国賊」という主張とピッタリ重なるのです。デビット・アトキンソン氏は、菅義偉政権の求めに応じて、中小企業の合従連衡による規模の拡大と生産性向上を進言しています。これは、実は日本経済が真の競争力を取り戻すには正当な政策なのですが、右の参政党と、左のれいわが一斉に反発しているのは興味深いです。
つまり、オーナーは一人だけ公私混同でチマチマした社長ライフを満喫、残りの労働者はヘトヘトという構図を、「古き良き中小企業の活力」と勘違いしているのです。参政党の場合は、そのような地方のオーナーから政治献金を期待しているという「だけ」かもしれません。後は、れいわの場合は、反原発はまあ彼らの「看板政策」ということなのでしょうが、行政のデジタル化も、自動運転車も、スマートシティも「新しいものには反対」という姿勢です。
ですから、ある意味では真の守旧派、保守派といってもいいわけで、ある程度この社会の成り立ちを理解している人、いや、一定の世代以下の人々には見向きもされないことになります。
ということで、自公連立与党はガタガタ、保守野党は「野党ビジネス」にアグラ、左派政党は富裕層向けだったり非現実の世界に没入、というわけで、全体的に見て日本の政治風土は事実上崩壊寸前ということが言えます。
そんな政治風土を象徴しているのが、8月24日に共同通信が配信した同社の世論調査結果です。23、24の両日、全国で電話世論調査を行ったものですが、自民党が参院選で敗北した責任を取り、石破茂首相が「辞任するべき」との回答は40.0%で、前回の7月の調査から11.6%減少し、「辞任は必要なし」57.5%の方が多くなったというのです。
つまり石破氏の辞任は必要ないという数字が、過半数、それも57%超えという数字になっているのですが、問題は支持率です。この57.5%というのは「辞めなくてもいい」数字であって、支持率ではない、ここがミソです。
では、支持率はどうかというと、35.4%しかありません。前回の7月の数字からは12.5ポイント上昇していますが、不支持は49.8%で依然として支持を上回っています。
では、自民の次の総裁にふさわしい人物を聞いたところ、高市早苗氏が24.5%でトップ。2位は小泉進次郎氏で20.1%、石破首相は3位で13.1%だそうです。よく考えると意味不明なのですが、世論の心理としては、
- 石破氏が辞任せず、次回の総裁選でも続投:13.1%
- とりあえず石破支持:35.4%
- 当面は石破の辞任は必要ない:57.5%
ということで、かなり微妙に数字が異なっています。つまり、現在の政策が正しいとは思わないし、石破氏のリーダーシップが数年続くのには87%近い人が反対しているが、現在の「石破おろし」は42.5%しか支持はないというわけです。
この数字のバラツキですが、そこにどういうニュアンスがあるのかは、非常に難しい解釈になります。
「声高に石破おろしを叫ぶ人は、裏金議員などなのでイヤ」
「対米交渉があるので、当面の交代はない」
「でも、現在の日本の状態は全く満足できないので、代わって欲しい」
「正規の任期を全うして規定通り総裁選をやるべき」
「自分が自分がという人は嫌い」
というようなニュアンスは何となく感じられます。では、こうした矛盾したような曖昧な感情をもっている世論は未成熟なのかというと、決してそうではないと思います。問題は「実行可能な範囲内の複数の選択肢」として、国の方向性が整理されて、それぞれの政党が責任ある「政権担当公約」として有権者に提示されるということが全く不十分だと言うことです。
「自公与党が割れ野党との集合離散」しかない解決策
その意味で、やはり一番の問題は保守野党の多くに「当面は野党ビジネスに徹したほうが得」だという姑息な態度が見えることだと思います。これを解決するには、やはり自公与党が割れて、野党との集合離散をやって選択可能で、政権担当能力のある2セットの勢力に再編成されることだと思います。
左右のポピュリズムが跋扈するのも、そのような選択肢がはっきり提示されないことが原因です。
image by: Shutterstock.com
MAG2 NEWS

 1 ヶ月前
16
1 ヶ月前
16



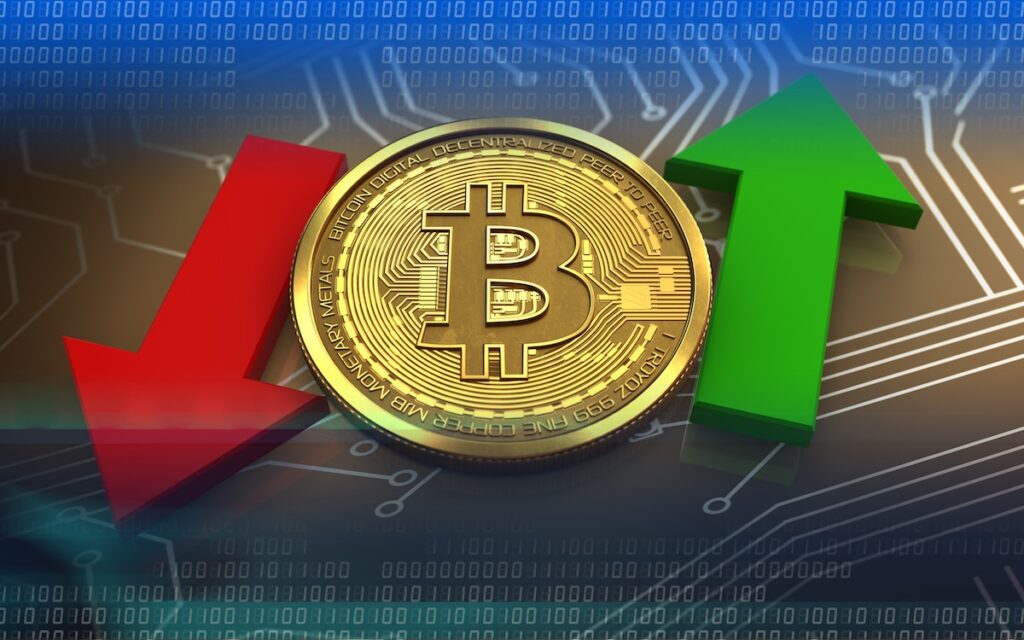

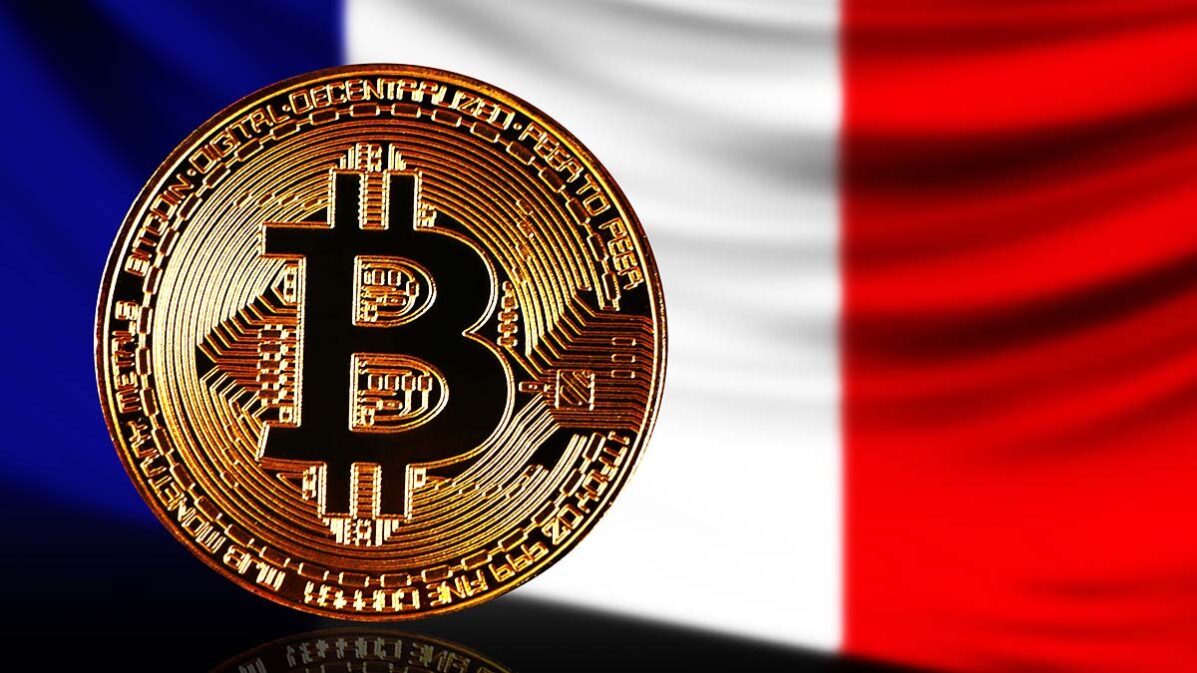


 English (US) ·
English (US) ·  Japanese (JP) ·
Japanese (JP) ·