
10日に発表された自公連立の解消をきっかけに、大混乱に陥った政局。そもそも公明サイドが「アレルギー反応」を明確に示していた高市総裁の誕生を、なぜ麻生太郎氏はバックアップしたのでしょうか。今回のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』では作家で米国在住の冷泉彰彦さんが、麻生氏が小泉進次郎氏ではなく高市氏を「選択」した理由を、「カネ」を軸に据え詳しく解説。その上で、今後浮上しうる「連立シナリオ」について考察しています。
※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/メルマガ原題:政局大混乱、結局はカネの世界か
結局は「カネ」?リスク満載の「政局大混乱」はなぜ起こったか
公明党の連立離脱により、26年(途中下野による中断あり)にわたって続いた自公の連携が崩壊しました。この間、公明党は1999年10月に正式に「小渕内閣」の連立に参加。以降は「森」「小泉」「安倍(1)」「福田康」「麻生」の各内閣、一旦は下野したものの、自公政権が復活すると再び「安倍(2)」「菅」「岸田」「石破」という各内閣を連立で支えたのでした。
ここで、政局は大混乱に陥っています。まず自公の選挙協力が終了することで、小選挙区では自民、公明の当選の可能性が大きく損なわれます。ですから、仮に現時点では国民の信を問うべきだとして、石破内閣が解散総選挙に踏み切ると、かなり難しい局面が来ます。自民も公明も議席を減らすでしょうし、国民、維新、立憲が「それぞれ難あり」という中では大勝ちは難しい、そんな中で、参院だけでなく衆院でも左右のポピュリズム政党が躍進して、全体のカオスは更に深まることが予想されます。
では、このようなリスク満載の混乱状態はどうして起こったのか、そして、今後の展開としてはどのようなシナリオが考えられるのか、少し引いた視点を設定して、考察してみたいと思います。その際に一つのツールとして、今回の混乱の真の原因は、イデオロギーや軍事外交ではなく、「カネ」、つまり財政、経済社会に関する政策の問題だという軸を設定することにします。そうすると、見えてくるものがあるからです。
まず高市自民党ですが、報道されている通り現時点での高市体制というのは、高市+麻生体制になっています。では、どうして麻生太郎氏が、土壇場で小泉ではなく高市を担いだのかというと、大きく2つの理由があると考えられます。それは、小泉より高市のほうが「財政規律にはプラス」でかつ「高市のほうが構造改革がマイルド」ということです。
小泉進次郎氏の場合は、今回の総裁選では封印していましたが、農業改革と雇用改革を政策の柱としています。具体的には、JA解体と民営化、そして解雇規制の緩和という2点です。これは、都市部のグローバル企業にはメリットが有り、その中での勝ち組労働者にもメリットがありますが、全国的には選挙には「向かない」政策です。
そして、麻生太郎氏という、いわば「地方名望家の大親分」的な存在からは、現時点では認められない政策なのだと思います。JAを壊し、解雇規制を緩めた場合に、自民党の地方票は崩壊し、大都市圏でも票を失うという計算が背景にはあると考えられます。
一方で、麻生氏が高市氏を担いだ、恐らくは最大の理由としては、小泉より高市のほうが結果的には財政規律を守る、という感触であったと考えられます。勿論、高市は「サナエノミクス」と称して財政出動や給付・減税などのバラマキをそれこそMMT理論(現代通貨理論=通貨発行権は事実上無制限)に近いノリで語ってきてはいます。
公明が連立離脱と選挙協力拒否に至った最も合理的な見方
ですが、その積極財政とバラマキというのは、一種のイデオロギーのようなものであり、右派のイデオロギー的言説が「その場のパフォーマンス」であるのと同時に、財政に関しても、そこまで真剣ではない、そう考えることができます。一方で、小泉の場合はより世代が若い分だけ、日本経済の低迷には危機感があり、財政を出動するということになれば、本当にやってしまう、麻生はそのような警戒感を持ったのかもしれません。
というわけで、恐らくは改革のスローダウンと、財政規律の維持という2つの「譲れない政策」ということで、麻生は高市を選んだのだと思います。では、公明としてはこれが気に入らなかったのかというと、そこは少々説明が必要に思います。
公明としては、今年の6月に石破政権と合意した経済財政政策の方針(いわゆる骨太2025)があります。「物価上昇を上回る賃上げ」「地方創生」「資産運用立国」「安心安全の確保」「全世代型福祉と少子化対策」の5本柱です。高市総裁になっても、この合意について守られるのであれば、公明としては「離婚届」を突きつけるところまでは思い詰めなかったと思います。
この中で可能性があるのが「全世代型福祉」というスローガンです。どういうことかというと、「高齢者ばかりではなく、現役世代のことも配慮する」、けれども「やっぱり高齢者にも配慮する」というのが、この「全世代」という言葉の意味なんだと思います。そして、その高齢者への配慮という点で、現在問題になっているのが医療費の3割負担問題です。
これは確証があって申し上げているのではありませんが、この3割負担については、見えないところで、大きな葛藤、いや暗闘を生んでいる可能性があります。現時点では、制度がどうなっているのかというと、
- 70歳までは現役…………一律3割負担
- 75歳までの前期高齢者…基本は2割負担、高額所得者は3割
- 75歳以上の後期高齢者…低所得は1割、中所得は2割(※)、高所得は3割の負担
となっていますが、※の部分の2割負担については22年10月に1割から2割にアップ。但し、その際に一気にアップになる人は救済措置があったのですが、今回、この25年10月から救済措置が終わります。
高齢の引退世代を多く支持層に抱える公明の場合は、この問題は大きなテーマであると思います。公明党=創価学会というのは、60から70年代の経済成長の中で、企業組織票でも組合員ではないために帰属先のない集団を徹底的に掘り起こして組織化した集団です。その構成員は、大都市圏とその近郊の商店・自営業者と専業主婦という特殊な特性を持っていました。
つまり商店会とPTAという地盤をどんどん攻めて作り上げた組織と言っていいと思います。ですから、最初はカネがあり、けれども帰属先がない、特段の利害関係がないことから、世代の問題もあって理想主義と平和主義の党として活動していました。資金力についても俗に「財務」と言われた集金をやって潤沢な物があったようです。
ですが、21世紀に突入するにあたって、支持層の高齢化が顕著になったのです。端的に言って、どうして野党から与党に転じて政権に入ったのかというと、公明の場合は自分たちの主張を通すためではなく、自分たちの支持層の高齢化を受けて高齢者の権益を守るためであったと考えられます。であるならば、今回、連立離脱と選挙協力拒否という「思い詰め方」に至ったのは、その高齢者の権益、ズバリ後期高齢者医療費の問題があったと見るのが最も合理的です。
全くのファンタジーとしか言いようがない国民民主の政策
では、公明党にしてもこの点を堂々と主張すればと思うのですが、実際は難しいのが実情です。団塊世代が年を追うごとに投票所に行けなくなっている中では、有権者の層の世代交代は顕著です。そんな中で、「75歳以上の2割負担はきついので優遇(※の部分)を延長して欲しい」とか、「できれば1割負担で」というような主張をすれば突っぱねられるのは明白です。
現役世代からは、子育てと物価高で大変な中、自分たちは所得にかかわらず3割負担なのに、経済大国時代を謳歌してきた高齢者が1割とか2割というのは「あり得ない」という声が来るのは当然です。また、そのような世代が投票所に来るようになっている現在、世代間格差を修正するために、後期高齢者の優遇を見直すという機運は広がっていると思います。
そんな中で、恐らくは麻生=高市ラインの動きの中に、公明としては絶対に見過ごせない一線を超えるものがあったのに違いありません。この問題は、表に出れば現役世代の世論が炎上して「全世代3割負担」という声が大きくなる性格のものです。ですから、公明は堂々ということはできず、「靖国ガー」とか「外国人ガー」などというイデオロギーの話でウヤムヤにしていますが、本丸は「後期高齢者」だと思います。
さて、仮にそうだとすると、公明は「実は提携できる相手が共産党ぐらいしかいない」という状況になっていると思います。衆院で24議席を持っているにもかかわらず、連立の足し算マトリックスで自由に動けないのは、このためと考えられます。
公明についてはそのぐらいにして、問題は国民民主です。まず、ここまでお話してきたように公明が後期高齢者の医療費2割、1割負担の維持にこだわっているのであれば、国民民主とは水と油だということは言えます。国民民主は、2割負担をハッキリ打ち出すとともに、高齢者の医療制度に現役世代の組合等からの拠出を「カット」して、現役の保険料を3割削減するとしているからです。
更に、国民民主の「手取り」政策というのは、所得減税+地方税減税+消費減税(一律5%)が加わって、更に「ガソリン暫定税率+二重課税廃止」「電気代値下げ」というセットになっています。一見するとバラ色の政策ですが、一言で言えば「財源は明示されていない」のです。
ですから全くのファンタジーとしか言いようがありません。勿論、手取りを増やし、消費減税をすれば景気には多少プラスになるかもしれません。ですが、その景気のプラス分とそれによる税収増では、この数10兆円単位のマイナスは埋められません。強行すれば、日本国債はどんどん世界市場で厳しい評価を受け、日本円がジワジワ売られるということになると思います。
国民民主は、安保防衛では昔の民社党のように、あるいは新進党のように、基本的に戦後秩序と日米同盟を重視する穏健保守の立場です。そうなのですが、仮に財政規律について、ここまでユルユルの話を本気で信じているのであれば、麻生グループとは全くの水と油になります。
可能性ある高齢者の利害に厳しい自民と維新の組み合わせ
一方で立憲ですが、こちらは安保防衛で穏健リベラルという立ち位置です。一部は権威主義の毒が回っている部分もあるが少数に過ぎません。では、国民はどうして立憲を嫌っているのかというと、「安保と原発で組めない」というのは実はタテマエだと思います。
現在の野田党首を中心とした立憲というのは、実は「財政規律の党」だったりします。野田政権が自公とやった三党合意もそうですが、基本的に立憲というのは、戦前の民政党のように「都市の国際派インテリ」が支持の中核です。ですから、経済的には多少の余裕があり、そのために明日の生存への恐怖というのは軽く、明後日の破綻を気にすることが「できる」勢力です。
そのくせ、立憲というのは官公労とはズブズブで、この点は維新、特に東京維新(あんまり勢いはないですが)とは鋭角的に対立します。象徴的なのが、2008年以降の政権担当時に、当時の民主党が八ッ場ダムとかスパコンへの予算について「仕分け」をやっていた構図です。あれは、小さな政府論かというと、実はそうではなく「ハコモノのカネはケチって官公労の人件費は確保」という彼らなりの行動だったのです。
ということで、ここまでお話していたのを整理すると、
- 高市(=麻生)と公明は、高齢者福祉で組めない
- 公明と国民民主も、高齢者優先か現役世代優先かで組めない
- 立憲と麻生は財政規律では組めるかもしれない
- 麻生と国民民主は財政規律で組めない
- 維新と立憲は官公労利害のために組めない
という相互の関係性があると見ることができます。ちなみに、国民民主が立憲を嫌う場合、公明が麻生を嫌う場合に「イデオロギーや軍事外交」の対立がある「フリ」をしています。ですが、実はそうではなくて「カネ」の話が主という理解をしたほうが筋が通ると思います。
そうではあるのですが、とにかく「後期高齢者の1割、2割負担」というのは、強く主張すると現役世代から大炎上するので、「表向きの話題にはできない」のです。そんな中で、今のようなイデオロギーの対立が誇張されるという現象が出ているのだと思います。
一つ、「提携の可能性がある」のは自民(高市=麻生)と、維新の組み合わせです。これはここまで述べてきた議論の裏返しであり、高齢者の利害に厳しいということでは、組める可能性があるからです。
維新と自民が組むのには勿論、基本的な難しさがあります。というのは維新の本拠である大阪では、自民党府連は公明と選挙協力しながら維新と血で血を洗う抗争をしてきたからです。そして、大阪における維新は猛烈な勢いで「納税者の不満」を吸収してエネルギーにして、「極端な小さな政府論」を進めてきました。
ですが、仮に自民が公明と手切れになるのであれば、維新としては組む条件が出てきたことになります。更に、基本は小さな政府論である維新ですが「自分たちには成長政策もあるんだ」ということを実証したいのと、自分たちなりにカジノ権益の支配を目論んで万博をやったわけです。この万博が、「予想に反して大失敗ではなかった」中で「地場経済には確かにプラスになった」という流れの中では、自民党の支持母体との和解は可能になっていると思います。
仮に、大阪における維新のパワーと自民の利害が矛盾せずに提携できれば、移民には相当程度なプラスになります。維新の場合は、地方政策が皆無ですが、いくら納税者の反乱だと言っても、地方に「死ね」とは言えないわけで、自民としては政権に取り込んで懐柔することは可能だと思います。
立憲+公明で自民を切り崩し「石破首班」という構図も
問題は、これだけ物価高への恨みというのが全国に吹き荒れている中で、維新と自民(=高市+麻生)が組んだ場合には、財政規律を意識することと、納税者の視点から「バラマキ」には消極的になるということです。そうなれば選挙には勝てる要素がありません。ですが、仮の話、大阪をかなり取って、他は安全運転と落選バネで何とかするということであれば、全く絶望的ではないと思います。
勿論、それでいいのかというと、維新には、右派ポピュリズムの「やり過ぎ」という前歴はかなりあり、相当に危なっかしい面はあると思います。ですが、夢洲のIRでガッポリ儲けて関西の経済を回すという政策からは、外国人排斥という話は絶対に出てこないわけで、この一点においても、参政と組む可能性は少ないと思います。
ということで、これから国会が召集される21日(火)までの動きとしては、自民党(高市+麻生)と維新の提携が成立するかどうかを、注意深く見守る必要を感じています。もしかしたら、少数与党でもいいのでこの組み合わせで本格連立を組むかもしれません。
仮にそうした動きが顕著になった場合、危機感を持つのは地方や官公労だと思います。いくら自民党が現実主義だといっても、財政が危機的な中で、日本式の「小さな政府論」の本家ともいうべき維新が政権参画するのであれば、地方へのバラマキは縮小される可能性があります。維新はこれを条件にしてくるかもしれません。
その場合、地方に危機感が増幅するとして、その勢力が大きな仕掛けをしてくる可能性はあると思います。それは、立憲と自民党の地方組織が組み、そこに公明も取り込んで、「高市=麻生=維新の連携」に対抗してくるという可能性です。
では、具体的な数字はというと、衆議院(定数465、過半数233)において、
- 自民(196議席)+維新(35)=231
- 立憲(148)+公明(24)=172
が厳しく対立するという構図です。実際のところは、後者の場合は自民党を切り崩して、例えば石破首班などという仕掛けも含めて工作をすることになると思います。前者の場合は、自民の造反を最小限にしなくてはなりません。勿論、数字的には国民民主(27)がキャスティングボードを握るように見えます。ですが、財政規律と現役世代の利害ということから考えると、国民民主はテクニカルにこの「どちらとも組めない」わけです。
ただ、そのどちらも世論の圧倒的な支持を得ることはできず、そんな中で、早々になし崩し的に解散総選挙になるかもしれません。その場合は、仮に「良いタマ」を揃えることができれば、国民民主が大勝する可能性があります。玉木=榛葉ラインとしては、政権を取るのはその後でいいと考えているかもしれません。
いずれにしても、表面的にはカオスのような政局ですが、ストーリーの本筋はやはり「カネ」つまり経済にあるのだと思います。高齢者福祉か、現役の手取りなのか、そして財政規律をどうする、という部分で、組める・組めないというマッチングがあり、そのメカニズムはかなり重要だからです。
image by: Sean Pavone / Shutterstock.com
MAG2 NEWS

 2 日前
3
2 日前
3



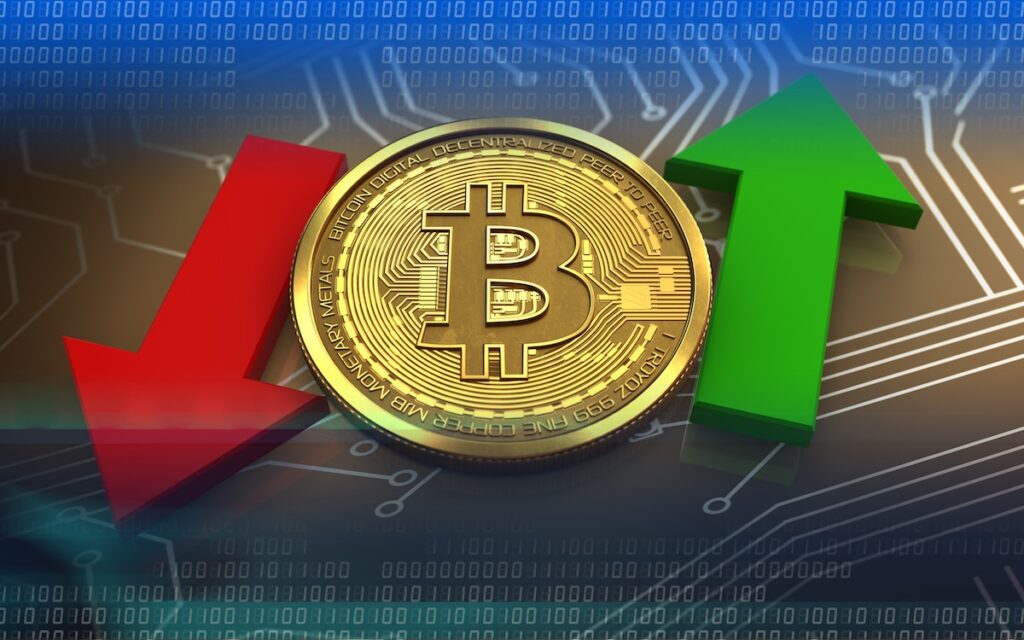

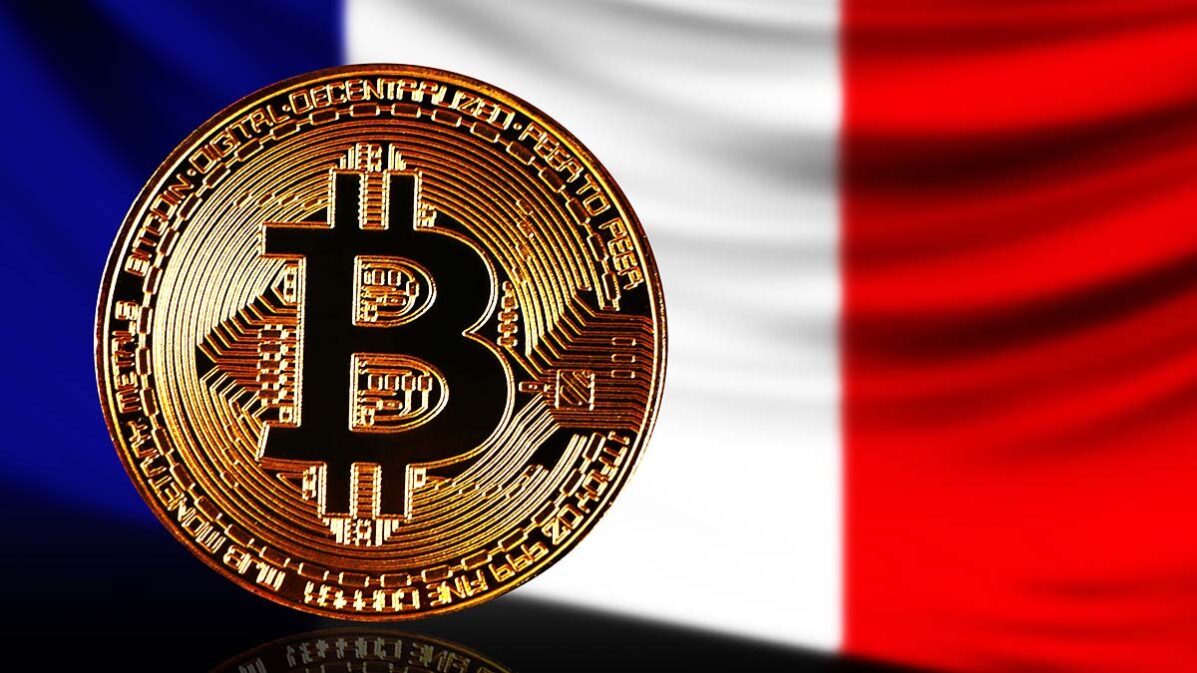


 English (US) ·
English (US) ·  Japanese (JP) ·
Japanese (JP) ·