
バブル崩壊以降30年あまり、低下傾向にある日本人の実質賃金。現在の水準は韓国を下回っているのが状況ですが、その元凶はどこにあるのでしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では元国税調査官で作家の大村大次郎さんが、日本の賃金低下を招いた最大の理由に「経団連」の存在を挙げ、そう判断せざるを得ない根拠を解説。併せて彼らが企業の利益を守るため、政府に突きつけてきた「要求」の内容も紹介しています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:外国人労働者を増やした黒幕とは?
【関連】元国税調査官が検証。外国人労働者が「日本人の賃金を下げている」は本当か?データから見えた“驚きの実態”
外国人労働者を増やした黒幕とは?
前回述べましたように、外国人労働者が増加してきたこの30年の間、日本人の賃金は下がり続けてきました。
【関連】元国税調査官が検証。外国人労働者が「日本人の賃金を下げている」は本当か?データから見えた“驚きの実態”
なぜこの30年で日本のサラリーマンの賃金だけが下がり続けてきたのかというと、いくつか理由があると思われますが、その最大のものは、「経団連」の存在です。
バブル崩壊後の日本は、「国際競争力のため」という旗印のもとで、政官財が一致して、「日本人の雇用を犠牲にして企業の生産性を上げる」というふうに傾きました。
それまでの日本経済は、「雇用を何よりも大切にする」という方針を貫いてきました。高度成長期からバブル期にかけての日本は、雇用を最優先に掲げてきたのです。高度成長を象徴する政策である「所得倍増計画」というのも、「日本人の賃金を10年で倍増させる」という計画だったのです。つまりは、国民の雇用、賃金を守ることで、国全体を良くして行こうという考え方だったのです。
企業の方もそれに答え、毎年のように大幅に賃金を引き上げました。日本では戦後の一時期は激しい労働運動がありましたが、高度成長期になると下火になりました。毎年賃金が上がるので、企業と闘争するまでもないという状況が続いたのです。
その結果、日本は高度成長期、バブル期にかけて、国民全体が自分の事を「中流以上だと意識できる」ような豊かな社会が出来上がったのです。いわゆる「1億総中流社会」です。そして、国民生活が豊かになれば消費も増え、それがさらに好景気を生むという好循環になっていたのです。
この記事の著者・大村大次郎さんを応援しよう
※ワンクリックで簡単にお試し登録できます↑
¥330/月(税込)初月無料 毎月 1日・16日
月の途中でも全ての号が届きます
企業業績のために人件費を下げるという愚策
が、バブルがはじけて以降、政官財のリーダーたちは、その方針を大きく転換してしまいました。企業業績を上げることを最優先であり、そのためには、賃上げなどはしていられない、ということになったのです。1990年代以降、外国人労働者を急激に増やしたのも、その流れの一環でした。
そしてその流れの中心となっていたのは、経団連という組織なのです。
このメルマガでも何度かご紹介しましたが、経団連とは、正式には、日本経済団体連合会といいます。経団連とは、上場企業の経営者を中心につくられた会合であり、いわば日本の産業界のトップの集まりです。経団連には、上場企業を中心に約1,400社、主要な業界団体100以上が加入しています。
日本経済団体連合会の会長は、財界の首相とも呼ばれ、日本経済に大きな影響力を持つのです。経団連は政権政党に対して、通知表ともいえる「政治評価」を発表し、その評価に応じて加盟企業に寄付を呼び掛けるのです。
たとえば、昨今では、経団連は安倍首相の政策を非常に評価していました。そのため、経団連は加盟企業に自民党への政治献金を呼び掛けました。自民党は、経団連の加盟企業から、毎年二十数億円の政治献金を受けており、収入の大きな柱になっているのです。いわば、経団連は自民党のオーナーのような立場なのです。当然、自民党は経団連の意向に沿った政策を行うことになります。
経団連は、バブル崩壊後の1995年、経団連は「新時代の“日本的経営”」として、「不景気を乗り切るために雇用の流動化」を提唱しました。経団連は、これまでの「雇用を大事にする」という方針を大転換し、「雇用を削ることで企業の利益を出す」という目標を掲げたのです。
そのため、「雇用の流動化」という名目で、「いつでも正社員の首を切れて、賃金も安い非正規社員を増やせるような雇用ルールにして、人件費を抑制させろ」と政府に迫ったのです。
これに対し政府は、財界の動きを抑えるどころか逆に後押しをしました。外国人労働者の大量受け入れが始まったのもこのころです。
しかも日本政府は1999年には、労働派遣法を改正しました。それまで26業種に限定されていた派遣労働可能業種を、一部の業種を除外して全面解禁したのです。
2006年には、さらに派遣労働法を改正し、1999年改正では除外となっていた製造業も解禁されました。これで、ほとんどの産業で派遣労働が可能になったのです。
そもそも製造業で労働者の派遣がこれまで禁止されてきたのはなぜでしょうか?
製造業などでは危険な作業が多く、労働災害が起こりやすいのです。そのため労働災害時などの責任を明らかにするためにも、企業が直接雇用することを義務付けていたのです。
また製造業など繁忙期と閑散期の差が大きい業種で、派遣社員を許してしまうと、「簡単に首を切る」ということにつながります。それでは、労働者の生活の安定が図れません。そのために労働者の派遣は厳しく規制されていたのです。
派遣労働が全面的に許されるようになると、当然、製造業者などは派遣社員を多く使うようになりました。派遣労働法の改正が、非正規雇用を増やしたことは、データにもはっきりでています。90年代半ばまでは20%程度だった非正規雇用の割合が、98年から急激に上昇し、現在では35%を超えています。
このように、従業員の賃金を抑制し、非正規社員を増やしたことが、「この30年で日本人の賃金だけが上がっていない」ということになった最大の要因なのです。
そして、この賃下げ政策の一環として、経団連は「外国人労働者の受け入れ」を強く働きかけてきたのです。
この記事の著者・大村大次郎さんを応援しよう
※ワンクリックで簡単にお試し登録できます↑
¥330/月(税込)初月無料 毎月 1日・16日
月の途中でも全ての号が届きます
外国人労働者を使って人件費を削減
経団連は、90年代から現在に至るまで、一貫して「外国人労働者の受け入れ拡大」を政府に働きかけてきました。
たとえば、2003年11月14日に出された「多様性のダイナミズムを実現するために“人材開国”を」と題された日本経団連の意見書では、「自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の締結が時代の波となっており、そのなかでも人の移動の自由化が議論されている」「しかしながら、日本では外国人がもつ力を発揮させる状況を戦略的につくり出そうという取り組みは必ずしも十分なされていない」「国は、専門的・技術的分野の外国人労働者の受け入れをより積極的に推進する方針を打ち出しているが、実際の取り組みは遅れている」などと述べられています。
この文言だけを見ると、非常に耳障りがよく「人の移動の自由化は世界の流れ」などと言われれば、その通りだなどと思ってしまう人もいるでしょう。が、経団連がやってきたことを重ね合わせてみれば、これらの文言の真の意図がわかってくるはずです。
経団連は、「外国人労働者の受け入れ拡大」を政府に促すのと同時に、「派遣労働の拡大」も働きかけていました。これらの方針は、「人件費をなるべく低く抑えたい」というのが本音であることは明白です。
そして、それを裏付けるようにバブル崩壊以降、日本の人件費は下げられ続け、現在では韓国よりも低くなってしまったのです。
【ご案内】元国税調査官の大村大次郎氏が、事業者向けの専門記事をプラスした「特別版」の有料メルマガを新創刊しました。さらに高度な情報をお楽しみください。
【関連】日本よ「こども家庭庁」をぶっ潰せ。知れば誰もが激怒する血税7.2兆円「中抜きし放題」の実態!省庁廃止で少子化が解決する理由(作家・元国税調査官 大村大次郎)
image by: 首相官邸
MAG2 NEWS

 4 週間前
11
4 週間前
11



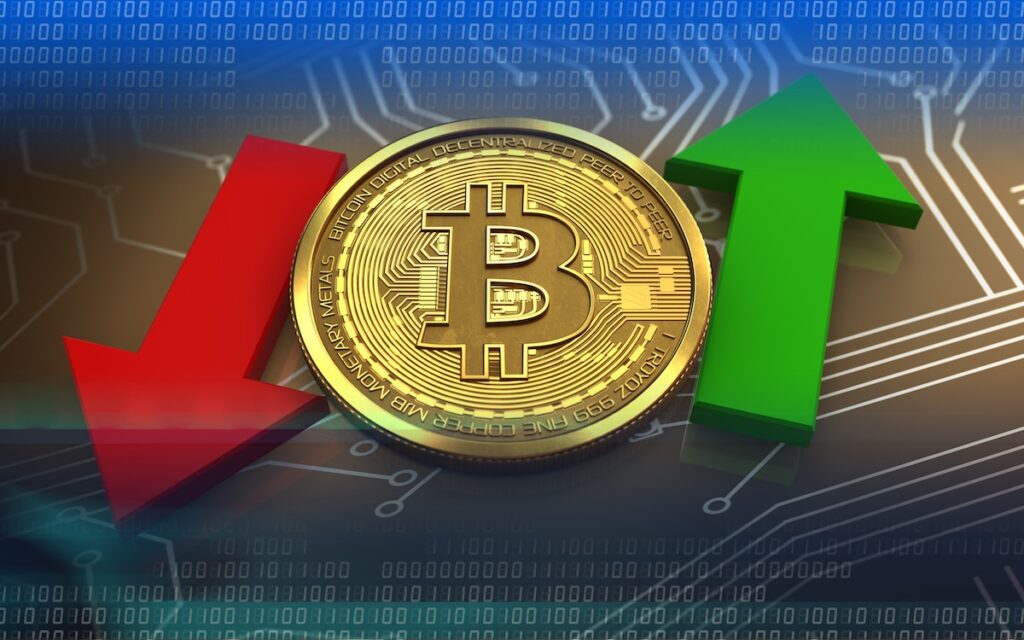

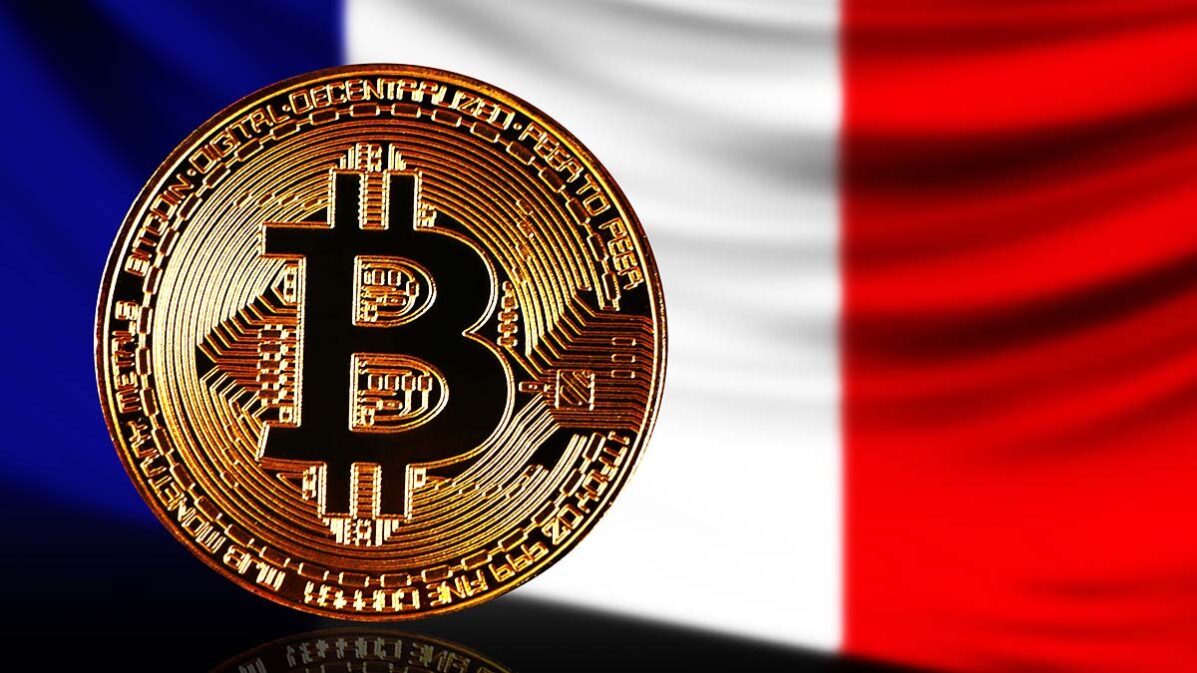


 English (US) ·
English (US) ·  Japanese (JP) ·
Japanese (JP) ·